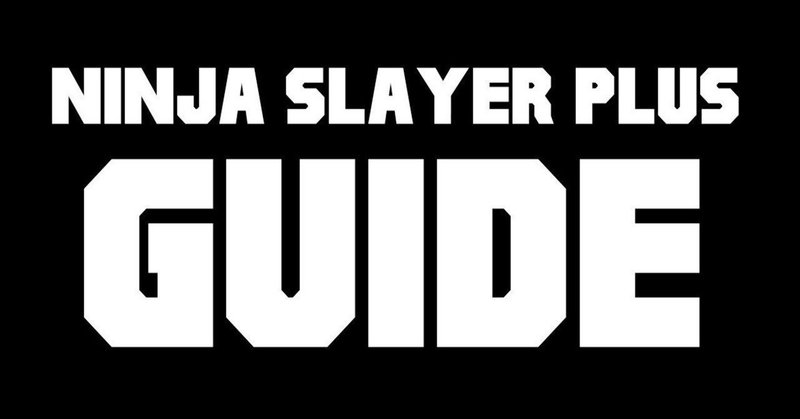ユーレイ・ダンシング・オン・コンクリート・ハカバ
この小説はTwitter連載時のログをそのままアーカイブしたものであり、誤字脱字などの修正は基本的に行っていません。このエピソードの加筆修正版は、上記リンクから購入できる物理書籍/電子書籍「ニンジャスレイヤー ネオサイタマ炎上2」で読むことができます。
ニンジャスレイヤー第1部「ネオサイタマ炎上」より
【ユーレイ・ダンシング・オン・コンクリート・ハカバ】
◆1◆
築数十年の十五平米ファミリーマンション、「ロイヤルペガサス・ネオサイタマ」の薄暗く冷たい和室で、合成綿布のフートンに包まった男が呻き声をあげていた。小さな網戸から忍び込んでくる重金属酸性雨の雨音と雨粒が、部屋に不快な湿気をもたらしている。
部屋の端には、天井まで積み上げられたUNIXサーバーの群が巨大なハカイシのように聳え、赤と緑のランプをホタルのように明滅させていた。その背後には、ウドンじみたケーブル類が束になっている。砂壁には若い男女と小さな子供が写った写真が額縁に入れられて、何枚も飾られていた。
男は裸だった。その逞しい肉体は一部が焼け焦げて黒ずみ、無数の傷跡ゆえに、まるで肉体がショウギ盤と化したかのような有様だった。男はひときわ大きな呻き声を喉の奥から搾り出し、苦しげに寝返りを打つ。「安らぎ」と毛筆体でプリントされたフートンが、まるで芋虫のように蠢く。
「フユコ…! トチノキ…!」彼が妻子の名を呼んだその瞬間、男の全身を覆う傷跡から血が滲み出し、その血は一瞬にして微細繊維状に編み上げられ、赤黒いニンジャ装束へと変わった。男の体は、湿っぽいフートンの中で、一瞬にしてニンジャ装束に包まれたのだ。
「あの時、あの時、何故俺は……!」男はフートンから右手だけを突き出し、空中で繰り返しチョップをくり出した。あまりの速さに衝撃波が生まれ、砂壁にかけられた額縁のひとつに小さなヒビが入った。
彼のチョップは、戦車の装甲をもひしゃげさせ、ソウカイ・ニンジャの首さえも一撃でへし折る。だが、今彼が戦っている相手は、肉体を持つ敵や鋼鉄のマシーンではない。彼の頭の中にだけ存在する、己の過去の記憶なのだ。
ヒビの入った額縁がタタミに落ちて転がった。写真の裏には、「フジキド家の宝」と書いてある。かすかな電子音と重金属酸性雨の雨音に塗りつぶされた暗闇の中で、男はかっと目を見開き、妻子の名を再び呟いた。彼こそはフジキド・ケンジ。今の名は、ニンジャを殺す者、ニンジャスレイヤーであった。
◆
ズンズンズンズズ、ズンズンズンズズ、ズンズンズンズズ、ズンズンズンズズ。非人間的で無機質なインダストリアル・テクノの重低音が、ジンジャ・クラブ「ヤバイ・オオキイ」から深夜のネオサイタマへと漏れ出してくる。
クラブのカンバンには、ヨウカンのように黒く真四角なサイバー調サングラスをかけたオイランの絵が描かれいる。サングラス部分は電飾仕様になっており、ミステリアスな薄笑いとともに「毎日楽しい」「実際楽しい」「金曜夜はユーレイ・ナイト」などの刹那的なメッセージを発し続けていた。
ここは、ネオサイタマ有数の富裕層居住地域「カネモチ・ディストリクト」の八番街。通称「カネモチ8」。平安時代には、丘の上に築かれた厳粛な霊場であったが、現在となってはネオ・カブキチョと並ぶいかがわしい繁華街のひとつへと堕している。
平安時代から続いたこの由緒正しいジンジャ・カテドラルも、今となっては、虚無的なカネモチ・ディストリクトの象徴と化している。ここは今から数年前に、オムラ・インダストリ系列のアミューズメント会社によって神主ごと買収され、サイバーゴス系クラブ「ヤバイ・オオキイ」へと変わったのだ。
ライオンの顔がプリントされたTシャツを着込み、威圧的に腕組みしたメキシコ系黒人ゴメスが、サイバー調サングラスをかけてクラブのトリイの前に立っていた。今夜は金曜だ。ユーレイ・ナイトに相応しい格好をしてこなかった愚かな客を追い返すのが、時給五百円でゴメスに与えられた仕事なのである。
実際、カネモチ8エリアにやってくる客の9割9分は、富裕層ではなく、富裕層と近づきになりたいと考えるカチグミ・ワナビー達だ。そういった連中の中には、暴力をもって何かを強制しないといけない無教養で無軌道な若者が、極めて多いのである。
「カラテ十三段」「殺人のライセンス」「日本語を理解しない」といった戦慄のメッセージが、ゴメスの顔の半分以上を覆うサイバー調サングラスの液晶面を右から左に流れ、彼の仕事を大いにやりやすくしていた。
トリイの前に新たなキャブが止まり、不健康そうなユーレイ・ゴスガールが姿を現す。ナチョス・ガムをくちゃくちゃと噛みながら、ゴメスは偉そうに頷き、顎をしゃくってクラブへの入場を促した。簡単な仕事だ。
しかし次の客の対応は、ゴメスに警察犬のような注意深さを求めた。笠をかぶり、ねずみ色のスーツの上にトレンチコートを羽織った50がらみのサラリマンが、手元のメモを見ながらトリイの前で立ち止まったのだ。その男は、トリイの向こうに聳え立つジンジャ・カテドラルを見て忌々しげに舌打ちする。
どう見てもクラブの客ではない。日本語のわからないゴメスにも、それは即座に判断できた。では、ネオサイタマ・シティコップの放ったマッポだろうか? そんな連絡は受けていない。よく見ると、笠の下に覗くくたびれた顔は、ほのかに赤く染まっていた。成る程、酒に酔ったサラリマンか。
ゴメスは逞しい胸板を強調してから、哀れなサラリマンに教え諭すように、サイバー調サングラスの液晶面を指差した。「カラテ十三段」「殺人のライセンス」「日本語がわからない」。まともな相手であれば、これを読んだだけで震え上がり、自分の間違いに気付いて立ち去るだろう。
「イチタロウの馬鹿め……」しかし、くたびれたサラリマンはそ呟きながらゴメスを無視し、この巨漢の横を素通りして、つかつかとトリイをくぐろうと歩き始めたのだ。ゴメスは丸太のような腕を伸ばしてサラリマンの笠をひっつかんで奪い取り、それを車道に向けてフリスビーのように放り投げた。
サラリマンは不機嫌そうに振り向く。ゴメスは軽い挨拶とばかりに、野太い右腕でサラリマンの顔面めがけてパンチをくり出した。サイバー調サングラスの液晶面には、まるでこの瞬間を待っていたかのように、偶然にも「ナムアミダブツ」の七文字が光る。
ゴメスの考えによれば、サラリマンは地面に這いつくばり、そのままゴメスに尻を蹴られてトリイの外に放り出されるはずだった。だが、ゴメスの放ったパンチは空を切り、それどころか、サラリマンがくり出した真のカラテ・パンチによって、彼のサイバー調サングラスは粉々に砕かれてしまったのだ。
「イヤーッ!」そのサラリマンはトレンチコートを威勢よく脱ぎ捨て、ねずみ色の背広をあらわにして、空中に三発ほどパンチと手刀を叩き込む勇ましいカラテの型を見せた。その背広の腰の辺りには、年季の入ったブラックベルトが巻かれており、この男が真のカラテ使いであることを暗示していた。
「さて、こんな事をしてしまっては、もう後戻りできんなあ」ひととおりカラテの型を終えると、サラリマンは地面に這いつくばるゴメスの巨体を見下ろしながら、悲壮感に満ちた調子で溜息をつく。「だが何としても、俺はイチタロウを連れて帰るぞお。鼻に輪を括り付けてでも連れ帰ってやる」
◆
その頃、ロイヤルペガサス・ネオサイタマの一室では、フジキドが今なお過去の亡霊と戦っていた。「俺がもし、あの時、ああしていたら……!」フジキドが苦しげに寝返りを打つと、彼の体を包んでいた赤黒いニンジャ装束は一瞬のうちに灰に変わって消え去り、傷だらけのフジキドの肉体があらわになった。
◆
ズンズンズンズズ、ズンズンズンズズ、ズンズンズンズズ、ズンズンズンズズ。サイバーテクノの重低音に合わせて、姿の見えないDJがネンブツのようなMCを繰り返し唱えながら、終末的なパイプオルガンを弾きならす。「ナムサン、ナムサン、ナムアミダブツ、ナムサン、ナムサン、ナムアミダブツ」と。
数百名を収容するジンジャ・クラブ「ヤバイ・オオキイ」のホール内は、ピンク、ターコイズ、オレンジなどのけばけばしいライトに目まぐるしく照らし出され、ホールの四方を取り巻く長大なショウジ戸には、ユーレイ・ゴスたちの影絵が刻み付けられていた。
無数のローソクが立てられた大燭台が天井から六つ吊られ、鎖を軋ませながら沈没寸前の難破船のように揺れて、炎の軌跡を描いていた。かつて大仏が鎮座していた北の壁にはスクリーンが置かれ、釜茹でにされるキリストや、逆さ写しのネンブツといった軽薄で悪魔的な映像が洪水のように映し出されていた。
ユーレイ・ゴスの服装は実に特徴的だ。男は病的なまでの細身といかり肩を強調したゴシック調のジャケットか、引き締まった筋肉をアピールする黒い網目のロングTシャツを着込んでいることが多い。
一方で、女はオイランじみた魅惑的な和服か、古城に佇む吸血鬼を髣髴とさせる純白か漆黒のドレスに身を包み、コルセットを巻き、桃のような胸元を強調していた。誰も彼も、最新の流行から外れない最新のユーレイ・ゴス・モードである。
また、ユーレイ・ゴスたちは皆、顔にオシロイを塗りたくり、死体のように目の周りを縁取りしている。また、男も女も紫や黒の口紅を塗り、ハカバの香りの香水を身に纏っている。さらに印象的なのは、皆頭にフンドシの紐を巻きつけ、その死体じみた顔を真っ白い布で覆っていることだ。
これは日本の伝統的な死装束であり、ニルヴァーナにおいてホトケと一体化するためにカンオケに入る死体だけにしか許されていない、神聖で厳粛な装いである。古き善き時代には、子供がちょっとでもこのような悪戯をしようものなら、祖先を侮辱するということで親に殴られたものだ。
だが、すべてのモラルと伝統的文化が商業主義によって破壊され蹂躙されたマッポーの世において、若者達は誰にも咎められることなく、死装束すらも何食わぬ顔で身に纏うのであった。ナムアミダブツ! なんたる背徳か!
しかし、もはや自分達には何一つ誇るべき美徳は無いのだというその事実を、若者達も少なからず自覚している。自分達がユーレイにも等しい無価値で虚無的な存在であることを皮肉るように、ユーレイ・ゴスたちは非人間的なビートに乗って、今夜もだらしなく踊るのだった。オーボンの夜の亡霊のように。
一方で、表面的なクールさにもこだわるユーレイ・ゴスたちは、すべてにおいて不吉なことを好む。このため、ジンジャ・カテドラル内で最も不吉な方角であるとされる北東の一段高くなったテーブル席「キモン」には、最も高いランクに属する客しか座ることを許されないのだ。
キモンに座るエリート・ユーレイの若い男6人は、ホールの中央で踊り狂う男女を見ながら、今夜の相手を物色していた。
「僕はあのオレンジ色の髪の男の子がかなりKawaiiだと思うね。君はどうするんだい、カーディナル・ダークソード?」と、全身をレザーボンテージで包んだマーシレス・エンジェルが問う。…もちろん、これらは一般的な日本人の名前ではない。彼らは皆本名を隠し、IRCネームで呼び合うのだ。
「そうだね、僕は……」漆黒のマニキュアを塗った華奢な指先を、そっと紫色の口元に押し当てながら、カーディナル・ダークソードと呼ばれた若者は気だるそうに返事をする「ウシミツ・アワーに、ブラッディ・アゲハって女の子と待ち合わせをしているんだ。そろそろ来るんじゃないかな」。
奇しくも時刻はウシミツ・アワー。ジンジャ・カテドラルの鐘が突き鳴らされ、不吉な音を奏でる。カーディナル・ダークソードとマーシレス・エンジェルがそろって目をやると、果たしてホールの南にあるショウジ度が開き、電子太鼓が打ち鳴らされ、新しい客がホールに姿を現した。
しかし、そこに現れたのは刺激的な服装に身を包んだユーレイ・ゴスガールではない。それは、ねずみ色の背広に身を包み、ブラックベルトを巻いた、明らかに異質な、酒に酔った薄汚いサラリマンであった。周囲のユーレイ・ゴスたちがサラリマンから離れ、彼は極彩色の海に浮かぶ岩のように孤立した。
マーシレス・エンジェルは、電子ジャーの中に入ったゴキブリを見るかのように嫌悪感をあらわにし、吐き捨てる「おいおい、ゴメスは何をやってるんだ。あの小汚い害虫をつまみ出させろ。急いでセキュリティを呼ばないと」。
その横で、カーディナル・ダークソードは顔を青ざめさせていた。フンドシで自分の顔が隠され、表情が読めないことを、これほど幸運に思ったことはない。何しろ、ヤバイ・オオキイに突如現れた闖入者は、他ならぬ自分の父親だったのだから。
ショウジ戸があちこちで開き、厳しいメキシコ人のセキュリティ・チームが数名現れて、一斉に侵入者のほうへと向かう。荒事に巻き込まれたくないユーレイ・ゴスたちは、モッシュピットを作るように距離を取りながらサラリマンを囲み、そこへセキュリティたちを導いた。
「面白いことになってきたわ…」ホールの西でそつなく踊っていたゴスガールの1人が、黒髪オカッパのカツラを脱ぎ、フンドシを取り去る。そこに現れたのは、ソーメンのようにしなやかなブロンドと、コーカソイドの顔立ち。彼女は小型カメラを構えながら、人ごみを掻き分けサラリマンの方向へと進んだ。
一方その頃、ロイヤルペガサス・ネオサイタマの一室では、フジキド・ケンジが今なお過去の亡霊にうなされていた。「俺がもし、あの時、ああしていたら……!」フジキドが苦しげにフートンの中で寝返りを打つと、傷跡から血が滲み出して繊維状に織られ、彼の体を包む赤黒いニンジャ装束へと変わった。
◆2◆
ジンジャ・クラブ「ヤバイ・オオキイ」のホールは血生臭い修羅場と化した。非人間的なユーレイテクノのビートに乗って、厳ついメキシコ人のセキュティたちが5人がかりで1人の泥酔サラリマンを止めようと襲い掛かる。顔色の悪いユーレイ・ゴスたちが、それをカブキショウのように取り囲んで見守る。
この程度の乱闘は、月に1~2度ある。一種の見世物のようなものだ。だが、いつもと違う点がひとつだけ。この泥酔サラリマンは、ネズミ色の背広の上から、くたびれたブラックベルトを巻いているのだった。
「イヤーッ!」「グワーッ!」サラリマンがくり出すチョップによって、意気揚々と向かってきた1人目のメキシコ人のサイバー調サングラスが割られる。「イヤーッ!」サラリマンは間髪いれず、相手のみぞおちに、内臓がハレツするほどのトーキックを決めた。「グワーッ!」
「イヤーッ!」「グワーッ!」サラリマンがくり出すチョップによって、意気揚々と向かってきた2人目のメキシコ人の首の骨が折られる。「イヤーッ!」サラリマンは間髪いれず、相手の股間に、股間がハレツするほどのトーキックを決めた。「グワーッ!」
「イヤーッ!」「グワーッ!」サラリマンがくり出すチョップによって、意気揚々と向かってきた3人目のメキシコ人が死ぬ。「イヤーッ!」サラリマンは間髪いれず、4人目のメキシコ人を殺すほどのトーキックを決めた。「グワーッ!」
「なんだありゃあ、ロドリゴの野郎、意気地のねえ」セキュリティ控え室では、オムラ・インダストリ製のプラズマ液晶モニタを眺めながら、バンザイ・テキーラとナチョ・スシを交互に口に運び、巨漢のメキシコ人がイガラ声で呟いていた。「生きて帰ってきたら、股間にマリアの刺青を入れてやるぜ」
「あなたの出番ってことですよ。スコルピオン=サン。何で出動してないんですか」ショウジ戸を開けて、光沢のあるスーツに身を包んだカチグミ・サラリマンが冷や汗をかいて入ってきた。「カラテですよカラテ。あんな奴が殴りこんでくるなんて前代未聞だ。万が一、金持ちの客に被害が出たら賠償問題だ」
「カラテが何だ」スコルピオンと呼ばれた巨漢は、ナイフでナチョ・スシの海苔巻きを刺し、タールのようにどす黒いショーユに浸してから傷だらけの唇の中へと押し込んだ。「メキシコ重犯罪刑務所で、両手に戦闘用の鎌を持った4人のカラテ野郎に囲まれた時のことだ。オレはまだ当時14歳だったが……」
「シャーラップ! タイムイズマネー!」カチグミ・サラリマンが切れた。「あなたとあなたのメキシコ人傭兵団を雇うのに、ソウカイヤにいくら払ってると思ってるんですか? 時給にして、ゴメスのそれのゆうに数千倍ですよ?」
「わかったよ、行きゃあいいんだろ、モモタ=サン」スコルピオンは、2メートル超の筋骨隆々の巨体を揺らして、だるそうに立ち上がった。黒Tシャツからはみ出した両の上腕に、凶悪そうな蠍の刺青が見える。思い出したようにコスタリカ産の葉巻を取り出して、無骨な指で挟んだ。「その前に、火貸せや」
「それをひと吸いしたら行くんですよ」モモタ=サンと呼ばれた出っ歯のサラリマンは、苛立たしげに金無垢のジッポライターを取り出し、火をつけた。しかし巨漢のメキシコ人は、葉巻を差し出す代わりにバンザイ・テキーラを一気飲みし、口元からスプリンクラーのような勢いで飛沫を噴き出したのだ!
「アイエエエエエエ!!!」テキーラの飛沫はジッポライターの炎で猛烈な火炎放射に変わり、モモタ=サンを火ダルマに変えた。ナムアミダブツ! これぞ平安時代より伝わる殺人ジュージツのひとつ、カトン・ジツに相違ない! ではこのメキシコ人はもしや……!
「オレはな、武勇伝を遮られんのが、一番嫌いなんだよ」スコルピオンはTシャツを脱ぎながら、吐き捨てるように言った。「アイエエエエエ!」モモタ=サンは火を消そうと畳の上を激しく転がったが、10秒も経たぬうちに、炙られて大根オロシを添えられたマグロの切身のようにおとなしくなった。
◆
「イヤーッ!」「グワーッ!」「イヤーッ!」「グワーッ!」ホールでは、泥酔サラリマンの大立ち回りが今なお続いていた。だが、彼も無傷ではない。時折メキシコ人のパンチが炸裂し、サラリマンの顔を豆ダイフクのように変形させていた。鼻血の量もおびただしい。おそらく鼻骨が折れているだろう。
サラリマンは目的地を知っていた。彼は迫り来るメキシコ人を次々となぎ払いながら、ユーレイ・ゴスの大波を掻き分け、北東のキモン・テーブルへと向かうのだった。キモンでは、腰を抜かしたカーディナル・ダークソードとマーシレス・エンジェルだけを残し、他の全員がすでにこの場を逃げ出していた。
「見つけたぞぉ、イチタロウ」泥酔サラリマンは、肩で息をしながら、カーディナル・ダークソードへと歩み寄る。そして血まみれの手で、震える放蕩息子の左手を取った。「父さんの会社が買収された。父さんはクビだ。退職金は出ないどころか、前のプロジェクトのハラキリをさせられて十億の借金だ」
「君の本名はイチタロウ? まさかね!」マーシレス・エンジェルは、汚物でも見るような顔でカーディナル・ダークソードを見た。 「そんな名前は知らない! 僕はこんな薄汚れたネズミのことなんて知らない!」カーディナル・ダークソード、イコール、イチタロウは、この世の終わりのように絶叫した。
「イチタロウ、一緒に帰るぞぉ。借金を返すために、父さんと一緒にサイバー・カラテドージョーを開こう。父さんの家は、三代前までは中国地方でエビを取りながらカラテドージョーをやっていたんだ。このブラックベルトは、江戸時代から父さんの家に伝わる、由緒正しいカラテの証なんだ」
「お前なんか知るものか!」カーディナル・ダークソードは、紫色の唇をわなわなと震わせながら言い放った。 「イチタロウ! しらを切るのもいい加減にしろ! 父さんはお前のIRCアカウントにログインして履歴を調べて、この退廃的ジンジャ・クラブを突き止めたんだ!」
「僕のIRCアカウントに、無断でログインした?!」イチタロウはもはや狂乱寸前の状態であった。逆上した彼は、浜辺に打ち上げられたホンマグロのように口をぱくぱくさせながら、胸元に忍ばせたゴシックナイフを震える右手で抜き、己の父親の心臓めがけて勢い良くそれを突き出した。
「イヤーッ!」「グワーッ!」だが無条件反射的に、サラリマンのパンチが息子の顔面へとしたたかにめりこんでいた。「イヤーッ!」さらに無条件反射的に、内臓をハレツさせるほどのトーキックが、息子のみぞおちに突き刺さった。「グワーッ!」
血を吐きながら倒れるイチタロウ。カランカランと虚しい音を立て、握っていたナイフが地面に落ちる。「イヤーッ!」サラリマンはネズミ色の背広を脱ぎ捨て、空中に三発ほどパンチを叩き込む型を見せた。それから怪鳥音とともに小さくジャンプし、革靴でナイフを踏みつけ粉砕した。インガオホー!
「イヤーッ!」興奮したサラリマンは、そのままキモン・テーブルの上に駆け上り、ハカイシ状の椅子に座っていたマーシレス・エンジェルの顔を散々殴りつけた。「グワーッ!」
「イヤーッ!」キモン・テーブルの上に勝ち誇るように立ったサラリマンは、ワイシャツも脱ぎ捨て上半身裸になり、空中に三発ほどチョップを叩き込むカラテの型を決め、ユーレイゴスたちに自らの強さを見せ付けた。その時だ。彼の背後に突如、黒い影が現れたのは。
「イヤーッ!」その黒い影はカラテ・サラリマンを背後から軽々と持ち上げると、そのままホールの壁に向かってウドンのもとか何かのように放り投げて叩きつけた。「グワーッ!」ジンジャ・クラブの分厚い木の壁が割れるほどの衝撃。猛烈な痛みがサラリマンの全身を襲った。
地べたに這いつくばったサラリマンは、おぼつかない視界のまま、自分を襲った新手の顔を見ようと体を起こした。
その巨漢は、下半身はニンジャ装束、上半身は裸、顔にはニンジャ頭巾という服装だった。丸太のように逞しい両の上腕には、凶悪な蠍の刺青が。背中にはマリアの図案と「サンタ・マリア」というゴシック体のカタカナが。腹には「悪いスコルピオン」とカタカナで彫られていた。全身刺青まみれである。
「ついにソウカイ・ニンジャのお出ましってわけね」ブロンドの女は小型カメラでスコルピオンの姿を撮影しながら、手持ちの違法改造モバイルフォンのアンテナを伸ばした。それから、モバイルフォンから生えたLANケーブルを、自分の右耳の左斜め上くらいに埋め込まれたバイオLAN端子へと接続する。
LANケーブルがジャックインされると、一瞬にしてナンシー・リーの精神の半分はサイバースペースへとダイヴした。これによって、彼女は通常のハードタイピングの数百倍の速さでIRCチャットを行えるのだ。一般人では受けることができない、違法サイバネティック技術のひとつである。
サイバースペースを飛ぶナンシー・リーの精神は、ネオサイタマ市警のサイバー・マッポ課に見張られた油断ならないIRC領域を高速で通過し、トリイの形をした電子暗号的シークレット・パッセージを8個くぐり抜ける。電子暗号をひとつでも間違えれば、彼女のニューロンは瞬時に焼ききれていただろう。
#NS_GOKUHI:NANCY:ニンジャスレイヤー! 今すぐ応答して頂戴! オムラ・インダストリとヨロシ=サン製薬とソウカイヤの3者を結ぶニンジャと腐敗の陰謀トライアングルが、いよいよ突き止められそうなの! あなたの助けが必要よ! ソウカイ・ニンジャらしきメキシコ人を尋問して!
しかし、ニンジャスレイヤーからの返答はない。ナンシーは精神を半分をジンジャ・クラブのホールに置き、ユーレイゴスたちの波に飲まれながらスコルピオンとカラテ・サラリマンの死闘を盗撮しながら、残り半分の精神力で、サイバースペースを飛び回りながらニンジャスレイヤーへの呼びかけを続けた。
◆
その頃、都心の片隅にあるロイヤルペガサス・ネオサイタマでは、フートンに包まったフジキド・ケンジが今なお過去の悪夢にうなされていた。「俺がもし、あの時、ああしていたら……!」
小さな網戸から忍び込んでくる重金属酸性雨の雨音と雨粒が、部屋に不快な湿気をもたらしている。今夜もまた、ストリートギャングとネオサイタマ・シティコップのカーチェイスや銃撃戦が、そう遠くないどこかでくり広げられているらしく、けたたましいサイレン音と銃声がしばしば雨音混じりに聞こえた。
だが、それらの音はフートンの中で芋虫のようにうごめくケンジ・フジキドの耳には届かない。彼の心は今、一瞬にして妻子を失いニンジャスレイヤーとして生まれ変わった、あの悲劇の夜へと引き戻されていた。そしていかなる光も、いかなる音も、今の彼の目と耳には届かないのだった。
「あの時、あの時、何故俺は……!」フジキド・ケンジは呻く。部屋の端に聳え立つUNIXサーバー群は赤と緑のランプを忙しく明滅させ、液晶面には「ユーガッタメッセージ」とカタカナが流れている。IRCメッセージ着信を告げる小鼓の電子音も鳴っているが、それら一切は彼の目と耳に届かないのだ。
◆3◆
スコルピオンに放り投げられ、壁にしたたかに叩きつけられたカラテ・サラリマンは、背中と頭からおびただしい血を流しながら立ち上がり、カラテの型を決めた。「イヤーッ! イヤーッ!」ゆっくりと迫り来るスコルピオンを威圧するためだ。だが、その気合もニンジャには通じない。
「カラテ野郎、よく聞きな」スコルピオンは指の骨をバキバキと鳴らしながら、キモンの隅にサラリマンを追い詰める。「オレは12から25まで、メキシコ重犯罪刑務所で過ごした。当時オレと一緒に刑務所に入ったギャング団の仲間は、3人に1人のペースで死に、5年後に生き残ったのはオレ1人だった」
「イヤーッ!」サラリマンは相手の話も聞かずに、ジンジャ・カテドラルの壁を蹴って三角跳びをくり出し、痛烈なジャンプキックを敵の顔面に食らわせた。 「グワーッ!」不意を突かれたスコルピオンのニンジャ頭巾が剥げ、無骨なメキシコ人の顔が半ば露になる。メキシコライオンのように凶悪な顔が。
「コロセー! コロセー!」ユーレイ・ゴスたちは、ブラッディなショウタイムに狂喜乱舞した。ホールに鳴り響く非人間的なサイバービートは、さらに速度を増す。大仏の代わりに据え付けられた大スクリーンには、ライブ中継されるサラリマンの顔と、「ナムアミダブツ」の不吉な赤文字が映し出される。
「イヤーッ!」サラリマンは、中腰の姿勢で両手を痙攣させながら前に突き出すシコの構えを取り、スコルピオンを威嚇した。テーブルの下に隠れたイチタロウは、痛みに耐えながら目をこすった。最高にダサいネズミ背広を着ていたはずの父が、カラテの鬼と化し、すぐそこでニンジャと殺し合いをしている。
会社をクビになったこと、自分にまで借金返済の手伝いをさせようとしたこと、そして何よりIRCアカウントをハッキングし、挙句の果てには自分に暴行を加えた父の身勝手な行動は、絶対に許せない、とイチタロウは怒りに燃えていた。
だがそれと同時に、目の前で死闘をくり広げている父の姿を見ていると、空虚なユーレイの胸にはおよそ不似合いな、無骨で野蛮な衝動がふつふつと湧き上がってくるのだった。おお、ナムアミダブツ! それは、あまりにも危険な英雄的衝動である!
血を唾とともに吐き捨てながら、スコルピオンは不敵な笑いを笑う。「カラテ野郎、オレは武勇伝を遮られんのが一番嫌いなんだよ」そして腰に吊った二本のナイフを両手で抜き、その刃を地面と水平に構えた。ナイフを持つ両腕も水平に大きく広げ、そのまま腰を落とす。この奇妙な構えは何であるか?
中腰の状態で、しかし一分の隙も無いまま、スコルピオンはサラリマンめがけ滑らかに迫ってくる。江戸時代に途絶えたニンジャ・クランのひとつ、サソリニンジャ・クランの構えだ。スコルピオンに憑依したニンジャ・ソウルは、恐るべき暗殺剣の使い手、サソリニンジャ・クランのゲニンだったのであろう。
サラリマンは間合いを保ちながら、敵の動きを観察する。(((何という構えだ。まったく隙がない。奴はまるで巨大なハサミを広げて獲物へ迫るサソリだ。恐るべきメキシコライオンサソリだ。……しかし見切った! 右のナイフの動きはフェイントだ。奴はきっと左から攻撃を仕掛けてくるに違いない)))
「イヤーッ!」意を決し、サラリマンはチョップの構えのまま突き進んだ。「アミーゴ!」それを右から迎撃する、痛烈なナイフの一撃! 「グワーッ!」サラリマンは一瞬にして、右手右足を深々と突き刺された。「グワーッ!」激痛のあまり床を転げまわる。「グワーッ!」このままでは殺されてしまう!
「イヤーッ!」残った力を振り絞り、ネックスプリングで立ち上がると、サラリマンはパンチの構えのまま突き進んだ。(((次は右から攻撃をくり出してくるに違いない!)))
「アミーゴ!」それを狙い済ましたように左から迎撃する、恐るべきサソリの一撃! 「グワーッ!」サラリマンは一瞬にして全身20箇所をナイフで突き刺された。「グワーッ!」激痛のあまりサラリマンは床を転げまわる。ヒノキ材の床板が血で染まる。「グワーッ!」このままでは殺されてしまう!
「イヤーッ!」最後の力を振り絞りネックスプリングで立ち上がると、サラリマンはジンジャ・カテドラルの壁で三角跳びを決めてから、イナヅマのようなジャンプキックをくり出した。(((サソリのハサミは水平方向にしか動かない。ならば上から!)))
「アミーゴ!」なんとスコルピオンは、オジギをするように前傾姿勢を取ってトビゲリをかわした上に、逆立ちをするように高く蹴り上げた右足の裏で彼を迎撃したのだ。恐るべきサソリの尾の一撃! 「グワーッ!」サラリマンは一瞬で全身の骨が折れた。
「コロセー! コロセー!」ユーレイ・ゴスたちは、さらなる流血に大興奮した。ホールに鳴り響く非人間的なサイバービートはさらに速度を増し、大仏の代わりに据え付けられた巨大スクリーンには、ライブ中継される血まみれのサラリマンの映像と、「インガオホー」の赤いカタカナが刻み付けられる。
#NS_GOKUHI:NANCY:何をしているの! ニンジャスレイヤー! このままでは、あのサラリマンが殺されてしまう! いくらカラテのブラックベルトでも、ニンジャが相手では勝てるはずが無いわ!/// ナンシーが絶叫する。だが、依然としてニンジャスレイヤーからの応答は無い。
「あなたたち、あのニンジャを止めなさい!」業を煮やして理性を欠いたナンシー・リーは、周囲のユーレイ・ゴスたちにヒステリックに怒鳴り散らす。ようやく掴みかけたスキャンダルの尻尾を、こんなところで逃がしてたまるものか。「この人数なら、時間稼ぎにはなるでしょう!」
しかし、ユーレイ・ゴスたちは人間的反応を示さない。彼らはバーカウンターで供されるズバリ・リキュールやバリキ・カクテルのオーバードーズによって、トリップしているからだ。彼らはサイバーテクノに合わせて踊り狂い、「コロセー! コロセー!」とネンブツのようにくり返すだけなのである。
キモンでは、二者の戦いが佳境に入っていた。いや、もはやほとんど一方的なリンチである。サラリマンはハンニャ・ヴァンパイアが描かれたキモン・テーブルの上に横たわり、死んだマグロのように無力だった。スコルピオンは殺人板前のように繰り返し彼にナイフを突き立て、ツキジじみた血飛沫を飛ばす。
スコルピオンは極度のサディストであった。重犯罪刑務所で拷問を受け不能になった彼は、ナイフで敵をいたぶることによってのみ快感を得られるのだ。傷跡だらけの唇に笑みを浮かべながら、スコルピオンは唸る。「17の時、クリスマスの夜だった。オレは壁に追い詰められ、全裸にされ、背中に刺青を…」
「イヤーッ!」 突如、スコルピオンの背中に繊細なゴシックナイフが突き立てられる。「グワーッ!」不意を突かれ激痛にあえぐスコルピオン。 振り向くと、そこには違法薬物シャカリキ・タブレットのオーバードーズで勇気を奮い立たせ、痛みと恐怖を克服したカーディナル・ダークソードが立っていた。
カーディナル・ダークソードはもう一本のゴシックナイフを抜き、切先を向けてスコルピオンを威嚇した。だが、ニンジャの前でそんなこけおどしは何の役にも立たない。スコルピオンはサソリ・ファイティング・スタイルのまま迫り、左右からのナイフの応酬で彼の全身を切り裂いた。「アイエエエエエ!」
肩に排気ホースを備えた戦闘服のような衣装に身を包み、テクノ・オコトを弾き鳴らすVJカンヌシが、「ナムサン」とインカムに向けて絶叫すると、その言葉がかすれた赤文字となってスクリーン上に躍る。サイバービートに合わせた真白なライトの明滅が、キモンの死闘を前衛映像作品のように照らし出す。
精神の半分をサイバースペースにダイヴさせたまま、ナンシーはキモンでくり広げられる殺戮ショウを盗撮し続けた。ピュリツァー賞級の凄惨な光景のはずなのに、純白のプラスチックのごとき無機質な音と映像に圧倒され、恐怖の感覚が麻痺してゆく。自分も実体無きユーレイであるかのような錯覚に陥る。
「マズイわ、本格的にマズイのよ…」未だニンジャスレイヤーからの応答は無い。これ以上サイバー・マッポ課の監視の目を逃れながらIRCチャットを続けるのは、テンサイ級ハッカーの腕をもってしても困難だろう。前頭葉のニューロンがチリチリいい始めた。 ……その時、誰かがぽんと彼女の肩を叩く。
「ドーモ、ナンシー・リー=サンですね?」 彼女が振り向くと、そこには黒尽くめのニンジャが立っていた。ニンジャ頭巾からはウドンじみた何本ものLANケーブルが延び、背中に負った銀色の通信デヴァイスに接続されている。その目元は360度を監視できる円環型サイバーサングラスに隠されている。
「初めまして。ソウカイ・シンジケートのネット・セキュリティ担当、ダイダロスです」と、ニンジャは機械合成音のごとき不吉な声を発した。 ナンシー・リーは背筋が凍りつくような恐怖と敗北感と死の予感を味わう。ウカツ! ここにいたソウカイ・ニンジャは、スコルピオン1人ではなかったのだ!
「あなたのIPアドレスを解析し、ここにいることを突き止めました。私のハッキング能力の前では、ファイアウォールなどショウジ戸も同然なのです」ダイダロスはマジックハンドのような動きでナンシーの首を掴んだ。偶然にも結び目がほどけてゴスドレスが脱げ、コーカソイドのたわわな胸が露になった。
「ナムサン、ナムサン、ナムアミダブツ」折しもテクノビートはフェイドアウトを始め、VJカンヌシは説教台の上で両手を後ろに組み、中性的な声でクライマックスを歌っていた。「ナムサン、ナムサン、ナムアミダブツ。ナムサン、ナムサン、ナムサン、ナムサン、ナ、ナ、ナ、ナ、ナナナナナナナナナ-」
その刹那! ジンジャ・カテドラルの暗い天井アーチ付近から八枚のスリケンが立て続けに射出され、ホールにいた誰の目にも留まることなく暗闇をしめやかに切り裂いて飛ぶと、ガントレットのようなサイバー入力デヴァイスを纏うダイダロスの右腕に小気味良くカカカカカカカカ、と突き刺さったのだ!
「アイエエエエエ!」ダイダロスは悲鳴を上げ、ナンシーの首根っこから手を引いてユーレイ・ゴスたちの波の中へと退却した。後方支援役であるダイダロスにとって、ニンジャ相手の戦闘は荷が重い。たとえ姿が見えなくとも、スリケンを使う敵がいれば、それはニンジャとみて間違いないのである。
ナンシーはドレスの裾で胸を押さえながら上方を見た。ステンドグラス、鐘、アーチ、どこにもニンジャの気配はない。だがよく見ると、鎖で吊られた六個の大燭台の揺れが、微かに大きくなっている。“それ”は南西のウラキモンから進入してきた。そして燭台を跳び渡り、キモンへと向かっているようだ。
ナンシーがキモンの上にある大燭台に目をやるのとほぼ同時に、金属の千切れる嫌な音がし、数百本以上のローソクを抱えた大燭台が落下する。ユーレイ・ゴスたちは誰一人気付かないが、ナンシーの高解像度カメラは、燭台の上で腕を組んで立つニンジャの姿を確かに捉えていた。
「グワーッ!」イチタロウ親子への暴力に夢中になっていたスコルピオンは、上空から大燭台が落下してくることに気付かず、その巨大な鉄塊に踏み潰された。そして……タツジン! 大燭台に乗ったニンジャによる絶妙な落下角度調節により、キモン・テーブル上の親子はその下敷きとなる運命を逃れたのだ。
分厚いヒノキ材とコンクリートで作られたジンジャ・カテドラルの床が陥没し、埋め立てられたハカイシの群れが、薬物汚染された土の中から顔を覗かせる。煙幕弾を撃ち込まれたかのような砂煙が立ち、キモンの一角は視界ゼロ状態となった。消えずに残ったローソクの炎が、ヒトダマのように揺らめく。
この落下で、さしものスコルピオンも死んだか? いや、そんなことはない。彼は間一髪で燭台の落下を察知し、床を殴りつけてヒノキ材を割り、その下に身を潜めていたのだ。煙がたちこめたことは、彼にとってむしろ好都合である。この程度の砂煙は、砂漠地帯で育った彼にとって何の障害にもならない。
スコルピオンは獲物を狙うライオンの眼で、燭台の上に立ち直立不動の姿勢を取る敵の姿を観察した。相手は赤黒いニンジャ装束に身を包み、口元は「忍」「殺」と彫られた金属メンポで隠されている。スコルピオンは知らないが、彼こそはすべてのニンジャを殺す者、復讐の戦士ニンジャスレイヤーであった。
ニンジャスレイヤーはまだ動かない。いつものフジキドならば、敵ニンジャを完全に殺すため、すぐに次の攻撃に移るはずだ。しかし、今のフジキドの眼は、キモン・テーブルに釘付けになっていた。……この良く似た顔の二人は、どうやら親子か。そしてどう見ても、もはや命を取り留める見込みは無かろう。
サラリマンの顔を見て、フジキドは愕然とする。彼の顔は、フジキドの部屋の壁にかけられた、結婚式の写真の中にあった。彼の名はヤマダ・ヨリトモ副係長。サラリマン時代を過していたフジキドの最初の上司にして、結婚式の仲人をつとめてくれた、大切な恩人の一人であった。何たる悲劇的再会だろう。
敵が心を乱しているのを見て取ったスコルピオンは、床下に身を潜めたまま、腰に吊ったバンザイ・テキーラを一気に飲み干した。そして燭台に残ったローソクの炎を利用して、カトン・ジツをくり出す。狙いは無論、大燭台の上に立つニンジャスレイヤーだ。
オムラ社製軍用火炎放射器も真っ青の炎が、ニンジャスレイヤーに襲い掛かる。しかしニンジャスレイヤーは、見事なブリッジで火炎を避けた。さらに三回バク転を決め、キモン・テーブルの上にひらりと着地する。フジキドの中に宿るニンジャソウルが、間一髪で危険を報せたのだ。
「ノープロブレッモ!」スコルピオンは両手にナイフを持ち直して床下から飛び出すと、サソリの構えでニンジャスレイヤーに迫った。サソリ・ファイティング・スタイルは無敵だ。カラテだろうがニンジャだろうが、オレのナイフで滅茶苦茶にしてやる。スコルピオンの胸には、慢心にも似た自信があった。
ニンジャスレイヤーはテーブルの上に片膝を付き、バズーカを撃つような姿勢を取る。それから両腕を素早く回転させ、ピッチングマシーンのようにスリケンを高速連射した。スコルピオンの弱点が飛び道具であると、一瞬にして見抜いたのだ。「イヤーッ!」
「グワーッ!」スコルピオンの両目にスリケンが突き刺さり、壊れたトマトジュース・ディスペンサーのように血が飛び散った。スコルピオンはメキシコ語で罵詈雑言を吐きながら、闇雲にナイフを振り回す。ユーレイ・ゴスたちが十人ほど巻き添えを喰って血祭りに上げられた。
「イヤーッ!」ニンジャスレイヤーは高く飛び上がり、空中でしなやかに身をひねって上下を入れ替える。頭が下に、脚が上に。それからジンジャ・カテドラルの天井を蹴って、自由落下速度にニンジャの脚力を加え、恐るべき亜高速のスピードでスコルピオンめがけ急降下した。
死のドリルがスコルピオンに直撃する。「グワーッ!」スコルピオンは腹に巨大な穴を穿たれ、その場に呆然と立ち尽くす。 ニンジャスレイヤーはスコルピオンの腹を正面から突き破り、相手の背後に着地していた。床のヒノキ材は真っ黒に焦げ、その周囲にはスコルピオンの臓物が散らばっている。
ようやく、キモンを覆っていた煙が晴れ始める。乱れていた音響システムが復旧を開始し、VJカンヌシの声とともにサイバービートがジンジャに戻ってきた。大燭台の落下からここまで、わずか十数秒の出来事だったのだ。ニンジャスレイヤーは、その場に立ち尽くすスコルピオンの傍へと歩いてゆく。
「貴様はソウカイヤのニンジャだな。オムラ・インダストリに雇われた、そうだろう? そしてオムラ社は、ヨロシサン製薬と組み、ここで違法麻薬を売買している。さあ、洗いざらい喋るがいい。そうすればカイシャクしてやる」鋼鉄メンポを通して、ユーレイですら恐怖に慄くほどの無慈悲な声が漏れた。
だがスコルピオンは笑った。「オレはな、看守を三十人叩っ殺して、メキシコ重犯罪刑務所を脱走したんだ。そして殺人マグロの海を泳ぎきって密入国し、スラムでラオモト=サンに拾われ、ここまで上り詰めた。ラオモト=サンのためにも、お前には何も答えてやらねえよ。それに、お前はここで死ぬんだ」
「アディオス!」不意にスコルピオンの体が爆発し、ジンジャ・カテドラルのホールを真昼のように照らした。異常を察したニンジャスレイヤーは、スコルピオンの体が破裂する1秒前に、素早く5回バク転を決めて爆発を逃れていた。不運なユーレイ・ゴスたちが、数十人ほど巻き添えを喰ったようだ。
スコルピオンが放った最期のカトン・ジツは、ヒノキ材で作られたジンジャ・カテドラルをたちまち火の海に変えてゆく。数百名近いユーレイ・ゴスたちは、太陽の光を浴びたユーレイのように慌てふためき、ホールの四方にあるショウジ戸を突き破りながら逃げていった。
半裸のまま床に倒れたナンシー・リーの姿を認めると、ニンジャスレイヤーは風のように駆け寄り、彼女を抱え上げた。ニューロンに損傷を負ったのか? 爆風の衝撃を受けたのか? それとも極度の恐怖で失神したのか? いずれにせよ、彼女にはまだ息がある。それだけが、フジキドにとっては救いだった。
外からは、数十台のパトカーのサイレン音が聞こえる。ネオサイタマ・シティコップに、ナンシー・リーを渡すわけにはいかない。ニンジャスレイヤーは彼女を抱き抱えたまま高く跳躍し、ステンドグラスを割ってジンジャ・カテドラルを脱出すると、そのまま重金属酸性雨に紛れて夜の闇へと消えていった。
◆
三十分後。オムラ・インダストリ製のフラッシュアウト・ボムによって全酸素を失い、強制鎮火させられた「ヤバイ・オオキイ」のホール内へと、ネオサイタマ・シティコップが調査のために乗り込んでくる。逃げ遅れた数十人のユーレイ・ゴスとVJカンヌシが、イワシの群れのように重なって死んでいた。
先程までのテクノビートが嘘のように、ジンジャ・カテドラルは本来の厳粛な静けさを取り戻していた。天井は一部が焼け落ち、重金属酸性雨が淋しげにシトシトと降り注いでくる。濁った目を持つネオサイタマ・シティコップのマッポたちが、死体の数を指差確認して数え、その声だけが静かに反響している。
キモンの一角はバイオハザード・テープとコケシ・ポールで囲われ、ネオサイタマ・シティコップのマッポですら進入できない状態になっている。そこでは、明らかに異質な白衣姿の三人組が、ピンセットやシャーレを用いて実に興味深いサンプルの収集にあたっていた。
彼らの白衣の右肩には、ヨロシ・サン製薬から派遣されていることを示す黄色と黒の腕章が。そしてその胸元には、ソウカイヤのエージェントであることを示す……そしてソウカイヤの構成員だけしか知らない……交差する二本の刀と「キリステ」の文字を象った小さな金属製のバッジがあった。
彼らのリーダーと思しき長身痩躯の男は、胸に「いつもお世話になっております」「リー・アラキ先生」と書かれた、灰色のネームカードを吊るしていた。リー先生は焼け焦げたスコルピオンのものと思しき肉片を、何個かピンセットでつまんで培養シャーレに乗せ、何個かを自分の舌の上に乗せた。
「スコルピオン君は、いい被検体だったのだがネェ……」リー先生は、一切の感情のこもらない甲高い声で言った。「感謝したいネェ……。メキシコ人に対しても、ニンジャ・ソウルのアンセレクテッド・レザレクションは起こりうることを、彼は自らの肉体で証明してくれたのだからネェ……」
「ああ、まったくですわ、リー先生」オレンジ色のボブカットに黒ブチのセルフレームメガネをかけた女助手が、豊満な胸をリー先生の腕にさりげなく押し付けながら、手に持つ小型携帯扇風機を先生の手元に向けた。雑菌のシャーレへの混入と、それによるニンジャ・コンタミネーションを防いでいるのだ。
「フブキ・ナハタ君、シャーレはもういい。サンプルの回収は終わったよ」「あらそうですか」ナハタと呼ばれた女助手は、再びさりげなく両胸をリー先生の背中に押し当てた。「先生、あちらのテーブルの上にある焼死体は、どうしましょう?」
「ただの死体だろう? 私の時間を無駄に浪費させないでくれよ、フブキ・ナハタ君。私はニンジャ以外に何の興味も無いネェ……」リー先生はハンカチで鼻をかみながら言った。「あんなマケグミども、何千人集まろうと、1つのニンジャソウルの価値も持たないのだ……ン? ンン?!」
その時だ。おお、ナムアミダブツ! 何たる恐ろしい光景か! どう見ても完全な焼死体と思われていた、キモン・テーブルの上の死体が、突如立ち上がり、地獄の底から聞こえてくるような、怨念に満ちた禍々しい声で咆哮したのだ! 「ノロイ」と!
白衣姿の三人組は、恐怖に凍りついた。ホール内のマッポたちも、その場で金縛りになった。……だが、立ち上がった真黒の焼死体は前のめりに倒れ、テーブルから落ちて呆気なくバラバラに砕け散ったのである。
恐怖を科学的好奇心で克服したリー先生が、ゆっくりと這い寄ってその死体をくまなく調査するが、心音、体温、その他あらゆる生物学的条件に照らし合わせても、数秒前まで生きていたとは考えられない状況だった。では何故?
リー先生が偶然眼を落とすと、燭台の落下によって露になった無数のハカイシが眼に入った。その中のひとつに、古事記にも用いられているニンジャの暗号、スリケン・ルーン文字が刻まれたハカイシがあることを、熟練のニンジャ研究家でもあるリー先生は見逃さなかった。
これはもしや……死体にニンジャソウルが憑依したのでは? そう閃いた直後、ジンジャ・カテドラルにリー先生の甲高い哄笑が響き割った。ブースト手術によって常人の数倍の思考速度を持つリー先生のニューロンが、今まさにニンジャ・サイエンスのパンドラの箱を開けようとしていたのだ!
【ユーレイ・ダンシング・オン・コンクリート・ハカバ】終
<<<コメンタリーヘ>>>
「ニンジャスレイヤーPLUS」でヘヴィニンジャコンテンツを体験しよう!
![]()
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?