
【ミューズ・イン・アウト】
◇総合目次 ◇エピソード一覧
この小説はTwitter連載時のログをそのままアーカイブしたものであり、誤字脱字などの修正は基本的に行っていません。このエピソードは上記物理書籍に加筆修正版が収録されています。また、第2部のコミカライズが、現在チャンピオンRED誌上で行われています。
【ミューズ・イン・アウト】
「うえっ、こいつはひどいな。まるでツキジだぜ」チーフマッポが思わず口を押さえた。細い路地裏はあたかも、何十匹ものマグロがネギトロ・グラインダーに放り込まれたかのような大惨事だ。実際にはマグロではなく、ストリートギャング達であったが。
辺りには手足が何本も千切れ飛び、アスファルトは血に染まっている。抗争だろうか?だが、武器を持っている者はほとんどいない。ドラム缶で焼かれていたと思しきイカケバブの串を握ったままの腕さえある。そして「何だ、こりゃあ……?」チーフマッポは怪訝な顔で、死体のひとつの前で身を屈めた。
ギャング生首の眉間に突き刺さっていたのは、一枚のスリケンである。「クソ…面倒くせえな」チーフマッポは舌打ちし、それを引き抜くと、ポケットに仕舞った。「何か遺留品でも?」「何でもねえ。バリキドリンク買ってこい」「ヨロコンデー!」レッサーマッポは走ってゆき、雨脚がまた強くなった。
「次のニュースです。画期的なドゲザ・サービスを導入することで、追加コスト無しに上半期の株価を30%伸ばすことに成功したヨロコビ・マート社に対し、老舗コケシ・マート社の逆襲が始まります。コケシマート、トコロザワ・セントラル店から消費者の声を……」オイランキャスターの胸は豊満だ。
「出口で必ずドゲザされるのは気持ちがいいね」「毎回利用しちゃうわ」「……大好評です。しかしコスト削減のため、今後はオイランドロイドの導入も……」マッポーに向け加速する閉塞感。淘汰される人間性。「くだらないニュースばっかり。もっと報道すべき事件があるのに」食卓でマツモトが言う。
「ねえ、そう思わない?」食卓の半分以上を占領する書籍や資料の山。僅かな隙間から向こうを覗きこみ、マツモトが聞いた。「ああ、そう思う」男が本に目を落としたまま答える。「例えばそうね、生体LAN端子が人体に与える良くない影響とか……ねえ、そう、タケノコ・ストリートの話、聞いた?」
「さあ」ホンガンジは彼女が作ったスシを口へ運び、黙々とカロリーを摂取する。サイドだけをぞんざいに刈り上げた髪は実際伸び放題で、色褪せたベロア・ジャケットはまるでサイズが合っていない。彼は全く冴えない物書きだ。「タケノコ・ストリートで、テクノギャングが皆殺しにされた、って話」
「クズが大勢死んだんだろ?全く、胸のすくような話じゃないか」「でも、ここからすぐ近くよ?怖いと思わない?」「そう思うよ」ホンガンジは構想を練り、上の空だ。「ねえ、これは同僚のキコから聞いた噂だけど、ギャングの死体の額に、スリケンが刺さってたんだって……信じられる?」「いや」
「一切報道されてないけど、第一発見者のパルクール・ヒキャクが見たんだって。それを聞いてから、通勤時も怖くて落ち着かないの。だってスリケンよ。信じられないけど……もしかしたら……ギャング同士の抗争じゃなくって、ニンジャが……」「バカバカしい話だ、全くね」ニンジャなど実在しない。
「早く寝て欲しそうね、話しかけて欲しくなさそう」マツモトが溜息をつきながら食器を片付け始める。「ああ」「あなたのインスピレーションになるかと思ったのに」「感謝してるよ、実際ね」ホンガンジは最後のネギトロ・ロールを口に放り込み、資料集を抱えて、巣穴めいた作業部屋へと向かう。
「電話ドスエ」電子マイコ音声が鳴った。マツモトがLED液晶画面を確認する。ハイテック表示機能により、相手の名前が解る。「シトネ出版社の……マシモ=サンよ。どうするの?」「無視しといてくれ。君はエアロビクスにでも行ってきたらいい」ホンガンジはフスマを閉じて鍵を閉めた。
◆◆◆
「アイエエエ!まさかそんな事だとは知らなかったんです!許してください!」繁華街の路地裏で哀れなサラリマンが許しを請う。「ザッケンナコラー!」それを一括する恐るべき暗黒社会スラング!斜め上方では「暴力追放」「ヤクザ」「高速回転」などのネオン看板がバチバチと火花を散らしていた。
「アイエエエエエ!」サラリマンは恐怖で座り込み失禁!「バカハドッチダー!」ヤクザの横では高級オイランが高圧的に煙草を吹かす!「スッゾコラー!アッコラー!」ヤクザがサラリマンの襟首を掴む!「アイエエエエエエ!そんな事だとは知らなかったんです!」恐るべきマイコ・ポンビキの実態!
「知らなかったで済むかコラー!…アアー?……ダッテメッコラー?」ヤクザはここで、看板の上から回転着地した謎の人影に気付く。ひときわ大きいネオン火花が散り、介入者の姿を照らす。ナムアミダブツ!マイコ・ポンビキ現場に突如現れたのは……ニンジャ!両手に鎖鎌を持ったニンジャである!
「ザッケ……!」ヤクザセンスによって死の危険を察知した彼は、瞳孔の動きだけでサイバーサングラスを暗視モードに切り替え、チャカガンを抜く!だが「イヤーッ!」ニンジャの投げ放った鎖鎌が一瞬早くヤクザの腕を切断!「グワーッ!」斬り飛ばされ鮮血を吹き出す己の腕を見て絶叫するヤクザ!
「イヤーッ!」「グワーッ!」「イヤーッ!」「グワーッ!」「イヤーッ!」「グワーッ!」ダブル鎖鎌で容赦なくヤクザが切り刻まれる!おお……何たる公開処刑めいた一方的攻撃か!「アイエエエエエ!」「ニンジャ!ニンジャナンデ!?」オイランとサラリマンは腰を抜かし呆然とそれを見つめる!
ヤクザを踏みつけ、謎のニンジャは高級オイランを睨む。「どんな気分だ?」「アイエエエエエ……」「さあ答えてくれ、どんな気分だ?お前を守っていたヤクザは死んだぞ」「ど、どんな気分ですって?」「そうだ」彼はオイランを立ち上がらせ、腰帯を勢いよく引いた!「イヤーッ!」「ンアーッ!」
オイランは為す術無く回転し衣服を剥ぎ取られる!「アーレエエエエ!」壁にぶつかり転倒!ニンジャは鎖鎌を収め、歩み寄ってくる!それは逃れ得ぬ死だ!「アイエエエエエエ!」恐怖に呑まれたサラリマンが絶叫し、背を向けて這いずり逃げる!「ンアーッ!」おお、後方ではオイランの嬌声が……!
◆◆◆
「一体どうなってるの、凄いじゃない。日刊コレワに書評よ」マツモトが食卓の向こうのホンガンジに言った。彼の新作バイオレンス探偵小説「竹林に潜むジャックザリッパー」が好評を博しているのだ。「まるで別人のような饒舌な筆致……暴力のヴェールの影に仄見える妖艶なる想像力……ですって」
「ミューズが降りてきたんだ」ホンガンジはメモ帳に目を落としたままスシを食う。「つまり、どういう事?」マツモトが聞く。「いくらでも書けるって事さ、もっとスゴイ作品が。それでもっと金を稼ぐ」「ねえ、ファックする?」「今は気分じゃないんだ。サツバツとした光景が、頭から落ちちまう」
「解ったわ、邪魔ってこと。すぐに籠るんでしょ?」マツモトが溜息をつき、食器を下げる。「感謝してるよ」ホンガンジがフスマを閉じて鍵を締める。「続いては、タマ・リバーに今年も現れた三匹のラッコについての微笑ましい続報ドスエ……」TVからは珍しく明るいニュースが流れていた。
「もう駄目かと思ってたわ」「ラッコチャンが生きてて良かった!」「タマ・リバーが、実はそんなに汚染されてないんだって事」…街頭インタビューの声。「絶対に開けないでくれよ」ホンガンジがフスマを開き、また閉じた。室内から大音量の音楽が漏れてくる。「解ってるわよ」マツモトが返した。
◆◆◆
「まだファイル整理なんてしてたのかい、ハニー」「ごめんなさい。あと少しで終わるから」高層集合住宅の広い一室で、若い自我科医夫婦が語らう。「ヤブサメ運動シミュレータの調子が悪いんだ。ちょっと見てくれないか?」「UNIXの事はあなたの方が詳しいでしょ?」「あの機械は君の専門だ」
広大なリビング。素晴らしい臨場感と運動量を得られる3D運動装置。「別に変じゃないわ」「ワイヤフレーム虚無僧を射ても反応しないんだ。実際やってみて」「いいわ。ほら、何も変じゃない……ちょっと!二人乗り……なんて……アイエエエエエ」「働き過ぎの罰だ」「嫌、そんな……怒るわよ!」
KRAAAASH!不意にリビングのガラス窓が外側からの鎖鎌投擲によって割られ、LEDボンボリ灯にスリケンが突き刺さって火花を散らす!「何だ!?強盗か!?」男はカラテを構え、妻を守るように窓の側へと向かう。「まさか、ここは120階よ!?アイエエエエ!」女医が金切り声を上げる。
明滅するLEDボンボリ。暗闇の中に飛び込む謎の人影がひとつ。「クソッ、何で警報が作動しない!」男が手動で警報UNIXボタンを押そうとするが、その指先は鋭利な刃物によって切り裂かれた。「アイエッ!?」ナムサン!警報制御板とスイッチは、すでにスリケンによって破壊されていたのだ!
続けざま、闇の中でカマの刃が光った。恐るべきダブル鎖鎌の連続投擲!「イヤーッ!」「グワーッ!」「イヤーッ!」「グワーッ!」「イヤーッ!」「グワーッ!」男の首が切断され、女医の目の前に転がる!「アイエエエ!アイ!アイエエエエエ!」幸福に包まれていた家庭が、一瞬にしてジゴクに!
ひときわ大きくLEDボンボリが火花を散らし、書斎机へと後ずさっていった女医は侵入者の正体を知る。ニンジャ。ニンジャだ。まさか。ニンジャなど実在しない筈なのに。「夫を殺されるのは、どんな気分だ?」ニンジャが歩み寄り、闇の中で血に飢えた目を輝かせる。じゃらじゃらと鎖の音が鳴る。
「こ……来ないで!セプクするわよ!」女医は引き出しからデリンジャーを取り、こめかみに押し当てる。気丈なカチグミだ。「ところがそうもいかない」ニンジャの声には不気味なまでの冷静さと寂寥感があり、今しがた目前で展開された残虐カラテ行為との間に、猟奇的なコントラストを描き出す。
「そうもいかないのさ」ニンジャは距離を詰める。女医が意を決して引き金を引こうとした瞬間、「イヤーッ!」目にも留まらぬ速さでスリケンが投げ放たれ、デリンジャーを彼女の華奢な右手から奪い取った。直後、彼女は羽交い締めにされている。「ンアーッ!」まさにベイビー・サブミッションだ。
……やがて、暗い室内に危険な吐息と押し殺した嬌声。「あなた……狂ってるわ……」「狂っていたらどんなに良かったか。俺をカウンセリングしてみろ」ニンジャは粗い獣じみた息を吐く。女医はファック&サヨナラの恐怖とこの男の放つ超自然的アトモスフィアの前に、精神を破壊されかけていた。
「俺の頭の中にミューズが降りてきた。彼女は暴虐的で血を求める。それと引き換えにイマジネーションをくれる」「ンアーッ……続けて……」「あるいは逆だったのかもしれない。彼女は俺のニューロンをファックして力を与えた代わりに、イマジネーションという奴を、根こそぎ食い荒らしちまった」
「富士山……鷹……ナスビ……死のシンボル…」NRSによる一時的狂気に陥った女医は、自らの心理状態とニンジャの異常性を、象徴心理学を駆使して理知的に説いた。ボンボリLEDの火花が、彼らの背徳的シルエットをショウジ戸に投射する。「彼女はどんどん貪欲になっていく。心配でならない」
「ニンジャなのに……恐い?」「悪人を殺すだけじゃ満たされない。俺の想像力はいずれ枯渇する」苦悩に満ちた嘆息。「興味深いわ……私たちいい関係に」「知能指数の高い女を殺したくなったんだ。凄く興味があって。次の作品は凄いものになる」その声に邪悪な情熱を感じ取り、女医は戦慄した!
「作品……ですって……!?そんな……もしかして、あなた……アーッ!ンアアアアアーッ!」SPLATTTT!鎖鎌が閃き、女医は即死した。血飛沫がフスマを染める!サツバツ!「……ウハハハハハハハ!ウハハハハハハハハハハハ!」ニンジャは邪悪な高笑いとともに、身を仰け反らせて笑った。
◆◆◆
「今年初の雪がネオサイタマに……」深夜TVでオイランキャスターが和やかに笑う。「シトネ出版からIRC、三作目の原稿の事……」マツモトが不安そうに言う。「大丈夫、あと少しだ。これさえ書き切れば、俺の名声は盤石……」ホンガンジがマツモトの握ったスシを淡々と咀嚼しながら返す。
「体、大丈夫……?もうずいぶん、外にも出てないでしょ」「ああ、合意するよ」「シトネ出版の人、ちょっと性急じゃない?話題性があるうちに書けってのは解るけど……このままじゃ、書き上げる前にカロウシするんじゃないの?」「ああ、合意するよ」ホンガンジはまた手帳に目を落とし、上の空。
食卓の上に厳戒国境線めいて積まれた書物と資料の山。隙間越しに、マツモトは分厚い眼鏡をかけたホンガンジの険しい横顔を見た。物理距離は一年前から変わっていないのに、遥か地平の彼方へ行ってしまったようだ。「ねえ、同僚から聞いた都市伝説だけど、下水道に白いワニが群生してるんだって」
「全くおめでたいな」「想像力が豊かなのよ。以前は笑って話に付き合ってくれたのに。ねえ、心配してるの」「君の通帳に入ってるだろ、結構なカネが。温泉旅行にでも行って……」「ここは私の家よ?出てけっての?邪魔だから?」「待ってくれ、すまない。本当に感謝してるんだ。でも佳境で」
「これさえ書き上げれば、あとはもう……自動書記だって何だって、カネが入ってくる。そしたら全て終わりで……」「解ったわよ……」マツモトはホット・サケで酔いつぶれ、食卓に突っ伏して寝息を立て始める。「絶対に……俺の作業部屋に入らないでくれよ」「ええ……邪魔……しないわ……」
◆◆◆
……「ハッ!」マツモトは食卓から身を起こし、己のウカツを悟る。食卓の上にはスシの皿が放置され、ショーユが床にこぼれている。ウシミツ・アワーを告げるTV番組。彼女は二時間ほど眠りこけた。立ち上がると、背中にフートンがかけられているのが解った。
家事に取りかかる。彼女は窓から忍び込む風の寒さに身を震わせ、鼻を啜る。明日の仕事は大丈夫だろうか。「雪な……」ホンガンジとクラブで出会ったのも、一年前の雪の日だった。冴えない物書きだが、どこか放っておけない魅力があった。クラブにいた女性の中で彼女以外はそう思わなかったが。
泥酔した彼は、オスカーワイルドだかエドガーアランポオだか、マツモトの知らぬ古い作品について批評家気取りの客と議論した挙げ句、殴り合いの喧嘩。クラブから逃げ出し路地裏を逃げていた所を、バイオネズミ用電磁トラップにかかり気絶していた。マツモトが来なければ雪の中で死んでいただろう。
マツモトはふと、ホンガンジの作業部屋のフスマを見た。そしてゆっくりと、そちらに近づいていった。「迷宮入りかと思われていた自我科医夫妻殺害事件についてドスエ。過激派ハッカーカルトから本日犯行声明があり、ネオサイタマ市警はこれを……」TVからはぞっとしないニュースが流れる。
彼に知れたらどれほど怒るかは想像に難くない。酷い喧嘩を何度もし、現在では掃除すら許されない。何故今夜に限って彼女はフスマの先を覗いてしまったのか。無数の欺瞞とメガロ気分が蔓延するネオサイタマ・シティで、不意に心細くなったか。好奇心が閾値を超えたか。あるいは今を夢と思ったか。
鍵のかけられたフスマを微かに開く。漏れ出す音楽とUNIXの光。そして……冷たい風。窓が開いているのだと彼女は悟った。タイプ音が聞こえない。まさかホンガンジも眠りこけてしまったのか。あるいは……カロウシ。机の上の精密ドライバーで鍵を静かに開け、彼女は大きくフスマを開け開いた!
そこには……おお、ナムアミダブツ!ホンガンジの姿は影も形もないではないか!マツモトは窓へと急ぐ。僅かに隙間が空いていた。窓を開け、顔を出して外を見る。32階からの眺めは眩暈を催し、彼女は顔を引っ込めた。「アイエエエエ……まさか、締め切りが間に合わずに身投げ……」
動揺した彼女は右往左往し、作業机の上に、UNIX画面に、そして部屋の隅のクロゼットに、そして再び窓へと目をやる。ふと彼女は違和感に気付く。そして身体をクロゼットの側に戻す。片方の扉が開けっ放しにされたクロゼットの奥に、何か異常なものが見えた。マツモトはふらふらと歩いてゆく。
床に積まれた書籍や資料の山を突き崩しながら歩く。そしてマツモトは……見てしまったのだ。クローゼットの服の奥にかけられたニンジャ装束と、鎖鎌と、いくつものスリケンを。「アイエエエエエエ……」彼女は絶句し、口を押さえて後ずさる。
ALAS!彼女は禁断の武器庫を覗き込んでしまったのだ。「ああ、見てしまったか」背後から声が聞こえた。マツモトは振り返る。窓がいつの間にか大きく開かれ、雪の混じった冷たい風とともに、腰に二本の鎖鎌を吊ったニンジャ装束の男が立っていた。声は紛う事無くホンガンジのそれであった。
「マツモト=サン、俺はニンジャなんだ。いつかこの日が来るとは思っていた。終わりだ。もう全てが終わりだ」「アイエエエエエ……まさか……まさかこんな事だとは知らなかったの……ホンガンジ=サン……ニンジャ……ニンジャナンデ……!?」マツモトは狼狽する。
「これだけは信じてくれ。感謝していたんだ。あの夜、君が電磁トラップから助け出してくれなかったら、俺は死んでいた」彼はゆっくりと歩み寄る。鎖が静かに揺れる。「その後も、スシを食わせ勇気づけてくれなかったら、俺は依然として死んだままだった。感謝してる。そしてミューズが来たんだ」
しばし呆然とした後、マツモトが見せた反応は、ホンガンジのイマジネーションを超えていた。「アイエエエエ……お願い、行かないで……ニンジャでも何でもいいから……」彼女は涙を流し、ホンガンジを抱きしめたのだ。それが彼の胸を打ち、内なるミューズ……邪悪なるニンジャソウルを疼かせた。
「駄目だ!正体を知られたからには、俺は行かねばならん!」ホンガンジは左腕で彼女を抱き、優しい肉の感触に苦悩した。そして己の意志に反してメンポの奥で歪む口角と、スリケンを握り彼女の首筋を後ろから狙う右手を呪った。彼は震える右手を睨みつけ、どうにか抗おうとした。だが無理だった。
彼は超えてはならぬ一線を超え、ニンジャソウルの闇に呑まれた。血の涙を流しながら、彼はいまや己が何者になったかを悟った。右手の震えは止まった。そして右手に握られた鋭いスリケンが、マツモトの首に突き立てられようとした……まさにその時!「イヤーッ!」闇を切り裂き飛来するスリケン!
「グワーッ!」スリケンが右手の甲に痛烈に突き刺さり、ホンガンジのスリケンは紙一重でマツモトの首筋を掠めた!ゴウランガ!「おのれ……何者だ……!」ホンガンジは獣じみた殺意を剥き出しにして振り返り、邪魔なマツモトを放り捨てる!「ンアーッ!」
「Wasshoi!」ネオサイタマの死神は窓の外から回転着地を決め、断固たる殺意とともにアイサツする。「ドーモ、ニンジャスレイヤーです」「ドーモ、ブラッククレインです」彼は両手に鎖鎌を構えた。死神はカラテを構えた。壁に伸びた彼らの影絵を見ながら、マツモトの意識は遠ざかった。
「イヤーッ!」「イヤーッ!」「イヤーッ!」「イヤーッ!」「イヤーッ!」「グワーッ!」「イヤーッ!」「グワーッ!」「イヤーッ!」「グワーッ!」「イヤーッ!」「グワーッ!」……
……「グワーッ……」……「オヌシの新刊は出ぬ……これにて終わりだ……何もかも」……「貴様……は……何者なのだ……ニンジャスレイヤー=サン……」……「オヌシらを殺す者だ……ハイクを詠め」……
「……初雪な……」……「……もはや詠めぬ……おお、ミューズは去りぬ……」……「イイイイヤアアアアアーッ!」……「サヨナラ!」ブラッククレインは爆発四散!
……「……初雪な……」……
◆◆◆
「フハァーン?……それで、次の日起きたら、この有様になっていたと?」チーフマッポが欠伸しながらハンドヘルドUNIXを叩いた。「ハイ」マツモトは涙を拭い、鼻水をかみながら頷いた。ホンガンジの作業部屋はまるで局地的トルネードが吹き荒れたかのような有様だった。
「それで、何を見たんでしたっけ……?」「その……よく覚えてないんですが……ニンジャとか……スリケンを……」マツモトは気恥ずかしそうに答える。「まあ一応そういう決まりなんで、これ、記録しますがね……フハァーン……常識的に考えて、そんなこと起こると思います?」「いえ……」
「鶴……だったのかも……」「フハァーン……だいぶ混乱してるようですし、自我科でも行ってみたらどうですかね……。ま、こりゃ、物取りですな。捜索願いのほうは、こいつらに」チーフマッポはレッサーに後を引き継ぎ、尻を掻いて去った。調書にはニンジャの事もスリケンの事も書かれていない。
「オイ、高額納税世帯だから、丁重にな……フハァーン……」「ハイ」「ハイ」「ハイヨロコンデー!」夜勤明けでマグロめいた目のレッサーマッポたちが入ってきて、指差し確認を開始した。「鶴……」マツモトは床に転がった刃物傷だらけのハードカバー書物を拾い上げ、とぼとぼと食卓に向かった。
偶然にもそれは、古事記に語られしクレイン伝説に酷似していた。……雪の夜、罠にかかった哀れなクレインがいた。老夫婦がこれを助けると、数日後、美しい女が彼らの家に宿を乞うた。彼女は返礼として見事なシルクの反物を織った。しかし、部屋でそれを織る光景を絶対に見てはならないと言った。
高価なシルク反物を売り、老夫婦は豊かになった。だがある夜、老夫婦は絶対に見てはならぬと言われた部屋を覗いてしまったのだ。そこで彼らは見たのは、クレインが反物を織る恐るべき光景であった。己の正体を知られたクレインは飛び去った。そして帰って来なかった。
だがこの物語には腑に落ちぬ点がいくつもある。何故老夫婦は覗いてしまったのか?そしてなぜクレインは飛び去らねばならなかったのか? ……当然ながらこの説話にも、常人が知るべきではない恐るべきニンジャ真実や暗号が隠されている。だが今はそれを語るべき時ではあるまい。
「……ありがとう……」マツモトは傷だらけの書物を抱きしめ、涙を流した。鶴は反物の代わりに通帳にカネを残していったのだ。新たな人生を踏み出す時だろう。彼女にも、シトネ出版にも、マッポにも、全ては現代のゴーストストーリーか、あるいは彼女のメガロ妄想であるとしか考えられなかった。
じきに彼女は逞しく立ち上がるだろう。そうでなければネオサイタマでは生き残れないのだから。幸いにもニンジャリアリティ・ショックはしばしば、無辜なるモータルへの慈悲となる。それは荒波の如く押し寄せ、モータルの精神を掻き乱した後、引き潮めいて全てを奇麗さっぱり奪い去ってゆくのだ。
「…初雪な…」砂浜に一つ残された巻貝めいて、彼女のニューロンの片隅にはその詠み切れぬハイク・フラグメントだけがいつまでも残留した。その言葉を唱えるたびに、彼女はセンチメントと力を得るだろう。それを残した者の想いは定かではない。だがいずれにせよそれは、彼女の救いとなったのだ。
【ミューズ・イン・アウト】終
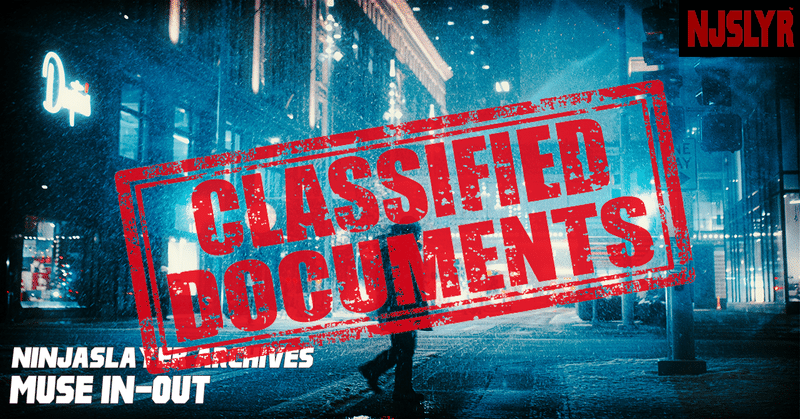
N-FILES(設定資料、原作者コメンタリー)
ネオサイタマのマンションの一室で、現実味の薄い同棲生活を送る作家のホンガンジとマツモト。不穏な殺人事件のニュースが流れ始めたのと時を同じくし、ホンガンジは作家として大成功を収め始めていた。その禁断のイマジネーションの源泉とは……!? ニンジャの暗い美しさに満ちた一編。メイン著者はフィリップ・N・モーゼズ。
ここから先は
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?

