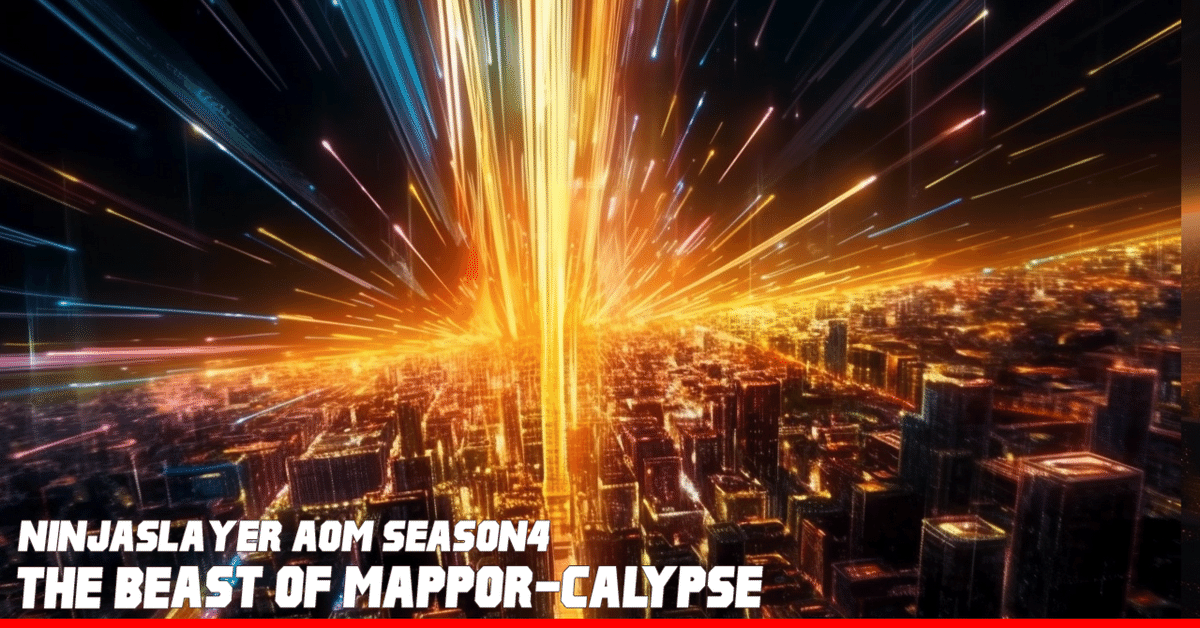
S4第9話【ビースト・オブ・マッポーカリプス後編】
1
「イヤーッ!」「イヤーッ!」「イヤーッ!」「イヤーッ!」「イヤーッ!」「イヤーッ!」「イヤーッ!」「イヤーッ!」「イヤーッ!」「イヤーッ!」「イヤーッ!」「イヤーッ!」「イヤーッ!」「イヤーッ!」「イヤーッ!」「イヤーッ!」「イヤーッ!」「イヤーッ!」「イヤーッ!」「イヤーッ!」
一糸乱れぬ、同期されたカラテ・シャウトのビートがネオサイタマに響き渡る。まるでそれは空に浮かぶキンカク・テンプルの邪悪な鼓動音だ。「イヤーッ!」そのなかで、ニンジャスレイヤーの叫びだけがタイミングを異にしていた。
赤黒く焼けつく足跡をコンクリートに刻み、マフラーめいた布をなびかせて、色付きの風となったニンジャスレイヤーは、遠く、黄金の光の柱を目指し高所を駆ける。ネオン看板「しけもく」のビルから「王子と健」のビルへ。「イヤーッ!」さらに跳ぶ。
屋上から屋上へ。猛スピードで進む彼の眼下、緑に沈んだネオサイタマの景色が流れゆく。まだら模様に、正常なネオンが生きる「安全地帯」が存在している。邪悪の及ばぬ場所だ。
黒山めいたカスミガセキ・ジグラットは今、アブストラクト・オリガミを太陽めいて、巨大なネオン・グラフィティ・アートを身に纏ってそびえ立つ。その威容は、異色の空に冷たく自転する黄金のキンカク・テンプルの光をせきとめ、限られた地域に日常をもたらしている。
だがそれも、かりそめのものだ。「イヤーッ!」「イヤーッ!」「イヤーッ!」「イヤーッ!」「イヤーッ!」「イヤーッ!」「イヤーッ!」「イヤーッ!」響き渡るカラテ・シャウトが証左である。
ビルからビルへ飛び渡りながら、ニンジャスレイヤーの視界は幾度かそのカラテシャウトの源たちを捉えている。これまでも、黄金光の下でネオサイタマ市民たちは狂ったようにセイケンしていた。今はそれにニンジャ達すらも連なっている。
「イヤーッ!」「イヤーッ!」「イヤーッ!」「イヤーッ!」ニンジャは黄金光の及ばぬ場所でもセイケン・ツキを行う。ニンジャスレイヤーは反射的に頭を押さえる。今でも彼のニューロンはじりじりと発熱している。狩りのたびに生じてきた赤黒のオリガミ。作り出した彼にとっても、その機序は謎だ。
赤黒のオリガミはニンジャスレイヤーと深い部分で繋がっていた。オリガミは力を発揮し、黄金光の波を拒絶する。当初彼は、その負荷の凄まじさに心砕かれかかった。ニューロンが焼け焦げ、爆発四散する寸前だった。内なるナラク・ニンジャのソウルに一時、肉体のコントロールを奪われるほどに。
「イヤーッ!」「イヤーッ!」「イヤーッ!」「イヤーッ!」だが、今は違う。彼は赤黒のオリガミの負荷を受け流すすべを身に着けた。その猶予をもたらしたのは、かつてニンジャスレイヤーであった男……サツバツナイト、フジキド・ケンジの、命を賭したチャドー・アーツ、「イエ・モト」であった。
マスラダは今再び、その折の「ソバ会合」に思いを巡らせた……。
◆◆◆
「ズルッ! ズルズルーッ!」「ズルズルーッ!」狩人メイヘムを倒し、そののち、あの決定的なジグラット富士誕生から、ほどなくして。
マスラダとフジキドはネオサイタマの安全地帯の一角、白いスモーク立ち込める屋台街において、しめやかなソバ会合の場をもった。彼らは隣り合ってソバを啜った。
フジキドは小瓶を取り、シチミの粉をソバにかけた。そして数秒の間を置いて、マスラダに尋ねた。「……使うか……」「ああ」マスラダは受け取り、自身のソバにもシチミを振った。「ズルズルーッ!」「ズルズルーッ!」二人のソバ啜りが再開された。
やがてマスラダが尋ねた。「その後、傷はどうだ」「イクサに間に合わせる」フジキドは答えた。「例のチャドーか?」マスラダは眉根を寄せる。「然り」頷くフジキドは、無理をしている。マスラダは見て取った。
傷とは、心臓である。マスラダの肉体を乗っ取ったナラクはフジキドの心臓を摘出した。だが、直後にコントロールを取り戻したマスラダは心臓を戻し、炎で強引に縫合した。
互いが互いを救った。ゆえに今、彼らは生きてソバを食べる事が出来ている。ジグラットの闇の中、動けるだけの力の戻りを待つ沈黙の状況を経て、彼らは多少打ち解けるに至った。言葉少ないフジキドと無愛想なマスラダは、おそらく、曲がりなりにもそうした瞬間を持つ必要があったのだ。
「オヌシが仕掛けられた狩りの儀式。その主催たるセトの陰謀を止める。私とドラゴン・ニンジャ=サンが追う邪悪なるニンジャ、ティアマトの存在がそこにある」フジキドはドンブリを置いた。「ムカデ・ニンジャの狩人に成り代わり、私はダークカラテエンパイアに潜入捜査を行った。ナンシー=サンに託した情報の通りだ」
「おれを襲った狩人は七人。その最後の一人がアヴァリス」マスラダは言った。「これまで通り、必ず仕留める。だが、主催の連中は今後も狩りを無限に続ける事が可能……そういう話だったな」「然り。カリュドーンの儀式に応ずる限り、イクサはダークカラテエンパイアの掌の上だ。何処かの時点で儀式を壊さねば、畢竟、奴らの邪悪な企みの成就が待つ」
「連中の好きにはさせない」マスラダは瞳に暗い炎を宿した。懐に帯びる冷たい質量を感じる。セプク・オブ・ハラキリ。そしてシナリイの言葉。「……この儀式、奴らには必ず後悔させる。コケにされたまま終わるつもりはない」
「オカワリ、イタシマスカ」店員がサイバネ・ノイズ塗れの声で尋ねた。二人が頷くと、程なく、ドンブリに新たな茹でソバが投入された。「「ズルズルーッ!」」
やがてフジキドが言った。「儀式主催のセトは、電子ネットワークに極めて長けた神話ニンジャだ。オヌシがアヴァリスとのイクサを始めれば、セトの仕掛けは必ず揺らぐ。かの者は儀式に深く根を張り、発生する巨大な電子情報のトラフィックを我田引水すべく対処するだろう。そこに隙が生じる。然るべき機を捉え、私がセトを叩く。オヌシは狩人とのイクサに集中せよ」
「……」マスラダはしばしフジキドを無言で見た後、呟いた。「……おれにとってはシンプルな話だな」二人は同時にドンブリを傾け、汁を飲み、ドンブリを置いた。置く音がユニゾンすると、彼らの表情は微かに苦笑めいた。
「もう一人いいかい……」ソバ会合が解散しようとした時、ビニール・ノレンをくぐり、フィルギアが横に座った。「わりとご無沙汰かな、サツバツナイト=サン……」アイサツもそこそこに、フィルギアは切り出した。
「なあニンジャスレイヤー=サン。知ってるかい……危険地帯に湧いて出るフェイスレスどもの状況が変化してる事をさ」「変化?」「ああ。妙な形を取り始めた。あれは……クロヤギだよ」
「クロヤギ・ニンジャ」フジキドが眉根を寄せた。「カリュドーン参加者の一人、アヴァリスの後ろ盾となっているヴァインの正体はクロヤギ・ニンジャだ」「そういう事だよね」フィルギアは割り箸を割った。「クロヤギ・ニンジャは太古のニンジャ。長命かつ不死身に近い。群体にして、その自我はひとつ」
「顔なしの影どもが、そのクロヤギに変わるのか?」マスラダが尋ねた。フィルギアは頷き、ソバを手繰る。「そう。フェイスレスには自我がない。クロヤギみたいな神話の化け物にとっては、アレを乗っ取って自分のブンシンの素材にするのも簡単だろうさ……オヒガンを通してね」「ブンシンを送り込んで、何をしている?」「見たところ……ニンジャを襲う。食ったり、さらったり」
「つながる」フジキドは国際探偵然とした推理を巡らせた。「クロヤギは、もはやアヴァリスと同一と見てよい。ナンシー=サンはセトのIRC空間で、アヴァリスめいた状態のヴァインを垣間見ている。アヴァリスは他のニンジャのジツを奪う力の持ち主……」
「クロヤギのブンシンにニンジャのジツを奪わせ、集めている、か」マスラダは呟き、目を光らせた。「アヴァリスはスゴイタカイビルの外に出てくる様子がない。ならば、鐘が鳴るまでに、おれは準備しておきたいと思っていた。奴がブンシンを使って外に干渉してくるならば、おれはそれを遡れる筈だ」
「ン……?」フィルギアは訝しんだ。マスラダは決意を固めた。「あちこちに出ているんだな? クロヤギは」「そうだよ」「潰して回る」「クロヤギを?」「ああ」「邪魔をして……負荷をかけるッて事……?」「多分な」「はっきりした理屈じゃないが……」「かまわない」マスラダは頷いた。「直感だが、大体わかれば充分だ。やる意味はある」「……ヒヒヒ……少なくとも、何かの邪魔にはなるか」
マスラダはドンブリの横に素子を置いた。「勘定を」「アリガトゴザイマス」サイバネ店主がオジギした。フィルギアはやや慌てた。「ああ、もう行くの?」「行く」「それなら俺もついて行こう。この件はもう神話の領域ッてやつだからさ。年の功ッて言うぜ」「好きにしろ」マスラダは去り際、フジキドを一度見た。フジキドは短く頷いた。
◆◆◆
「イヤーッ!」「イヤーッ!」「イヤーッ!」「イヤーッ!」カラテ・シャウトの反響を眼下に、ニンジャスレイヤーは一直線に移動する。やがて光の柱の源が見えてくる。緑の植物の柱。マルノウチ・スゴイタカイビルだ。マルノウチ市街上空にはエネアドを示すホロ旗が複数光り、剣呑であった。
「鐘が鳴ったな」走るニンジャスレイヤーのもとにフクロウのフィルギアが飛び来たり、並行して空を滑る。「気づいてるだろうが、下は無茶苦茶だぜ! いよいよ煮詰まってきた」「お前は平気か。フィルギア=サン」「ああ。ヤバイ圧力はギンギンに感じてるが……狂っちまったのは、ソウル憑依者の連中だ」フィルギアは畏怖を隠さない。
「あれは実際マズイ。ソウルはキンカクを通してもたらされる。多分、そこに関わる汚染だな」「感じる。キンカクとアヴァリスの繋がりを」ニンジャスレイヤーは言った。視界、スゴイタカイビル方向にはカリュドーン対戦者の所在を示す輝きが滲み、それを通して様々なニンジャ第六感の感応があった。
「それで? ニンジャスレイヤー=サン、お前の敵は何処にいる? スゴイタカイビルのあの光の柱か?」「そうだ」「正面エントランスから入る?」「いいや」ニンジャスレイヤーは否定した。「邪魔な連中の相手など、していられるか」哨戒するエネアド兵たち。やがてスゴイタカイビルが目と鼻の先。巨大な緑の柱の周囲に、剥がれた石塊が浮かんでいる。
「イヤーッ!」ニンジャスレイヤーは身体を捻り、ひときわ高く跳んだ。彼はビル周囲に浮かぶ石塊を踏んだ。たちまち脆く砕ける石塊を眼下に、再び彼は跳んだ。「イヤーッ!」闇の王の天守閣めいたスゴイタカイビル屋上をめがけ、赤黒の風は舞い上がってゆく……!
◆◆◆
「ン……何だ? 妙だな」見目麗しいエネアドサラリマンは、インプラント網膜の電子的揺らぎを訝しんだ。前方のUNIXルーム方向である。彼は一瞬の沈思黙考を経て、腰に帯びたケペシュに手をかけた。この程度のノイズはしばしば発生する。警戒しながら彼はUNIXルームに進んだ。その首に手がかかった。
「……! ……!」エネアドサラリマンニンジャの顔にメンポが自動装着された。拘束を逃れようともがく彼を、白い手はUNIXルームに引きずり込んだ。「……!」「……!」「……!」やがてユカノは制圧したサラリマンをUNIXルーム内のロッカーに押し込め、戸を閉めて、取っ手部分をチョップひと突きで破壊した。
「殺してはいません」ユカノが言った。「生体反応が警報のトリガーになっている可能性もあります」「うむ」サーバーを背にしたフジキドが厳かに頷いた。「荒事は極力避ける必要がある。今はまだ」『その通りよ』UNIXデッキのスピーカーからナンシーの電子音声。その傍ら、ナンシー本体はLAN直結中。
画面には論理タイピングされるコードが滝めいて流れ落ちてゆく。「長居はできんぞ」フジキドは言った。「今のサラリマンの不在が長引けば、それ自体を訝しまれる」『ええ。わかってる。でも今は実力突破はダメ。たちまち隔壁が落ち、オフィス内のエネアドニンジャ全てが向かってくる事になるわ』
モニタ映像に映し出されているのは、深奥に通ずる壮麗な社内門と、その左右で両手を交差させて立つ身長4メートルのニンジャ2名であった。直立姿勢でぴくりとも動かぬが、実際それは生きたニンジャである。『構造上、この先にあるこのゲートを必ず通過しなければならない。その際、戦闘は不可避になる。今仕掛ければ、敵の数は手に余る』「ヌウウ……」
『けれど、カリュドーンのイクサが始まれば、セトは処理にかかりきりになる。その時こそ動くタイミングよ。それまでは……SHIT!』フウウン……。モニタがブラックアウトし、ナンシーはLANケーブルを引き抜いて違法セッションをログオフした。「なんて速さ! 影を踏まないようにするのが精一杯。セト、とんでもないわ」
ナンシーは息を吐き、携帯ザゼンαを飲んだ。「それでも、雀の涙くらいの情報は得られた。見て」盗み取ったデータを携帯端末に表示し、フジキドとユカノに示す。「例のヒラグモ、覚えていて? スゴイタカイビルの地下に安置されているレリックよ」「うむ」「あれが儀式に果たしている役割は、当初の想定以上に大きいわ」
ナンシーの端末に、怪物じみた茶器のワイヤフレームモデルが現れ、ゆっくりと回転した。「ヒラグモは儀式の安全弁。ネオサイタマを丸ごと用いた巨大な儀式が自壊しないよう、この茶器の力が支えているの。加えてこの茶器は、キンカクからビルに注ぐ力を全てトラップしている」「セトの企みだな」
「セトはキンカクのエテルを茶器に蓄え、我が物にせんと?」ユカノが眉根を寄せた。ナンシーは続けた。「ある意味では、既に我が物にしている」ネオサイタマのワイヤフレーム地図に、黄金の枝が張り巡らされた。「現在、ネオサイタマは磁気嵐に包まれ、大規模な通信障害を引き起こしている。これはキンカクが及ぼした被害に上乗りした、セトのエネアド社の暗躍よ。ただ、手際が良すぎるの」
ナンシーは表情を曇らせた。「ごく僅かな時間で、ネオサイタマを飲み込んだ異変の影響を電子的に再構築し、インフラを乗っ取ってしまった。セトといえど、リアルタイムのタイピングだけでこれは不可能の筈……!」
「では、どういう事だ」「ネオサイタマの電子インフラに干渉するからには、電子的なコードを組む必要があるわ。セトも当然その手順を踏んでいる。でも、彼が取り扱うコードには、特定の暗黒メガコーポ特有のクセがあるの」
「それがエネアドではないのか?」「違うわ。エネアドはセトが手足として拵えたフロント企業に過ぎない。このアルゴリズムは、とある新興企業のもの。かつて私達の時代には、まだ存在していなかったカイシャ。名前は、アダナス」「アダナス……!」フジキドは唸り、拳を力強く握った。
「アダナスの狙いは何なのかしら……」ナンシーは自分の中で考えをまとめるように言葉を手繰った。「単なる技術供与? いいえ……そんな筈はない。アダナス社も儀式とヒラグモを取り巻くシステムに何らかの形で関与している可能性がある。詳細はまだわからない。とにかく、今わかっている事は、ヒラグモが儀式にとっての、ひいてはセトにとってのアキレス腱になるという事……!」
「ですが茶器は今、スゴイタカイビルに」ユカノは呻いた。「ええそうよ」ナンシーは頷いた。「スゴイタカイビルには今、有能なウキヨが潜伏してる。ヒラグモをソーシャルハックする事ができるのは彼女……コトブキ=サン」「なんという事でしょう」と、ユカノ。ナンシーは腕組みした。「私が彼女のガイドを試みなければ。その……」その時。ノイズが走った。
「来たわ」ナンシーがザゼンαの残りを一息に飲み干し、再びUNIXデッキに向き直った。「儀式が始まった!」「……!」「……!」フジキドとユカノは奥歯を噛み締めた。ナンシーは二人を一瞥し、頷いた。「ここは私一人で平気! 一気呵成に行くわよ!」「「イヤーッ!」」二人は部屋を飛び出した!
無機質な廊下を走り抜け、角を曲がった時、フジキドは漆黒に橙の光を灯すニンジャ装束、ユカノは金刺繍をあしらった赤のニンジャ装束に変わっている!ゴウランガ!サツバツナイトとドラゴン・ニンジャは、巡回エネアドクローンヤクザにトライアングル・トビゲリで襲いかかった!「「イヤーッ!」」
◆◆◆
「イイイ……イヤーッ!」高速車輪回転する赤黒の影が天高く跳ね上がり、上空のキンカク・テンプルの逆光となった。アヴァリスは両手をひろげ、牙をむき出し、笑った。赤黒の影は凄まじいドライブ回転を伴って落下し、アヴァリスの脳天に踵落としを突き立てようとした。アヴァリスは交差腕で受けた!
KRAAAASH! 二者の接触点を中心に放射状のカラテ風が吹き抜け、四隅のシャチホコ・ガーゴイルの中に詰まったドクロがバラバラと吹き飛んだ。「ゲーッ!」「ゲーッ!」彼らの上空を無数のカラスたちが羽ばたき、喚きながら旋回する!「イヤーッ!」「イヤーッ!」大地からはカラテ・シャウト! 天! 地!
バリバリと音を立て、アヴァリスの身体の数箇所に、赤黒い熱の裂け目が生じた。出会い頭の衝突から赤黒の影は後ろへ飛び退き、回転着地し……そのまま、オジギした。「ドーモ。アヴァリス=サン。ニンジャスレイヤーです」
「フフフ……フフフハハハハ」アヴァリスは肩を震わせ、笑った。たちまちその裸の上半身に沸騰する黒い上衣が溢れ、秀でた肉体を包み込んだ。ねじれた角はさらに迫り出し、イクサの高揚に軋んだ。「ハハハハハ……!」目を閉じ笑うアヴァリスの顔にメンポが装着された。彼は目を開いた。暗く燃える目を。そして彼はアイサツに応じた。「ドーモ。アヴァリスです」
2
「ようやく俺の番だ」アヴァリスは不敵に微笑んだ。「神聖なるオミクジの順番決めやら、カリュドーンの典範やら、実際くだらない限りだ。所詮あのセトがお膳立てした茶番だろうに、神聖もクソもない。そう思わんか?」「……」ニンジャスレイヤーは無言。
ここから先は
この記事が気に入ったらチップで応援してみませんか?

