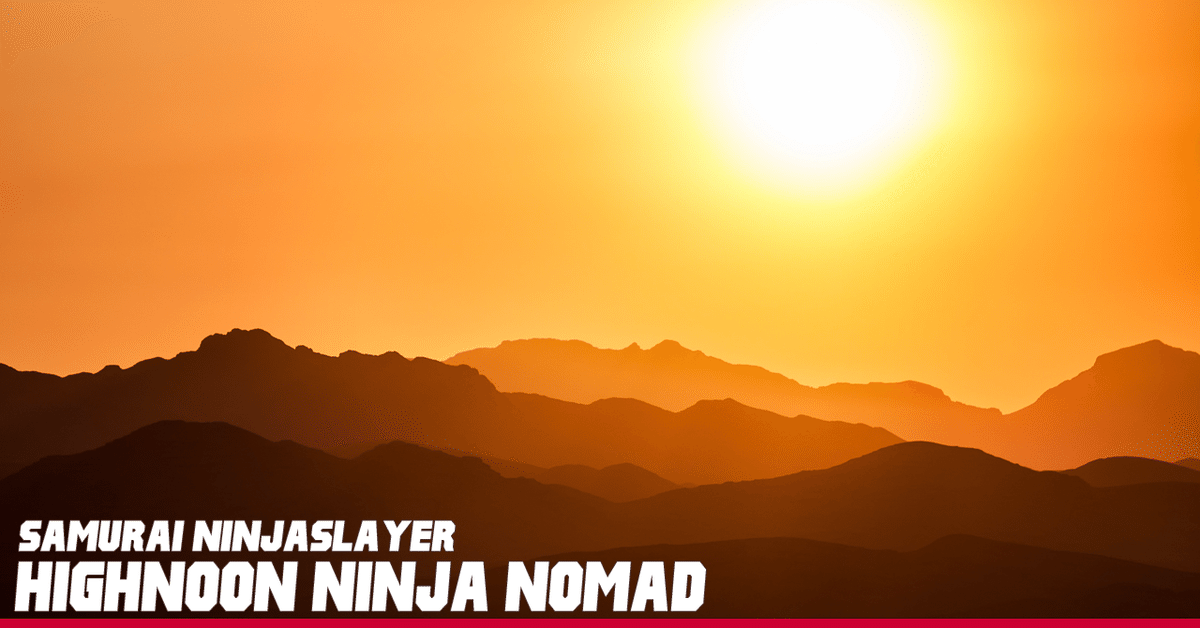
ハイヌーン・ニンジャ・ノーマッド(前編)
正午。ニンジャ。流れ者。
道標の向こうの松林に、行倒れの落武者を見つけた町人ユフコは、持っていた握り飯を渡し、藁を被せて家に戻った。「日が暮れたら戻りますゆえ、それまで持ちこたえて下さいませ」と云い残し。
家がある宿場町オミノロシはそこから徒歩で数分ほど。目と鼻の先であった。ここへ来てユフコは、初めて自分の行動が恐ろしくなった。落武者を匿ったと知られれば、即ち、死罪。命知らずにも程がある。だが、そうせずにはおれなかったのだ。
オミノロシの入口には老人が立ち、本当に見えているのかどうかも解らぬ白濁した目で、いつものように彼女の胸元などをジロジロと観察した。ユフコは両手を汗でじっとりと濡らしながら、西の職人通りへと向かった。途中、またも訝しむような視線が二つ三つ、酒場や長屋の暗がりから投げかけられる。大丈夫、いつものことだと自分に云い聞かせ、ユフコは平常心を保った。
かつて旅人で賑わった大通りも今は閑散とし、枯れた丘羊栖菜が、粉じみた風に吹かれて転がるのみ。宿場町オミノロシの空気は、重く淀んでいた。五年前に銀山の枯渇。さらに新たな宿場が海岸沿いに拓かれ、いまは訪れる者も無し。さりとて、出て行く者も無し。残った者は三百と少し。
何故街を捨て、移住しようとせぬのか。地方代官が銀山の再開発を検討しているからだ。今を耐え忍んで居座れば、再度この街が賑わった時に、労せずして大金を手にできる。だがそれは来年か。五年後か。あるいは永遠に来ないのか。仕事を失った町人の多くは、代官の命ずるまま、粗末な畑にケシを育てて糊口を凌ぐのみ。
ユフコは家に戻ると、息を吐き、囲炉裏の前に正座した。線香を焚き、御仏壇に供えられた位牌に手を合わせた。

日暮れ。髑髏じみた満月の下、ユフコは提灯も持たずに落武者のもとへと戻った。街道に人気は無かった。鈴虫の鳴く音だけが響いていた。落武者はまだあそこにいるだろうか。まだ生きているだろうか。道標までたどりつき、暗黒の松林を覗いた。
「お侍様、もう大丈夫です」
ユフコが呼びかけると、藁の中から呻き声が帰ってきた。ざわざわと藁の落ちる音が鳴った。「ヌウーッ……」落武者はぼろぼろの刀を地面に突き立て、それを杖代わりに立ち上がった。ぜいぜいと息を切らし、苦痛に顔を歪めながら。「かたじけない」彼は足を引きずりながらユフコのところまで歩いた。
一瞬、落武者の両目が血のように赤く輝いた気がして、ユフコは身震いした。だがそれは錯覚のようであった。月明かりに照らされた落武者の青白い顔はやはり、憂いを帯びた生真面目そうな侍のそれで、それでいてしかし、何かひとつの信念に向かって形振り構わず突き進まんとするような、危うげな色を帯びてもいた。どこか、亡くした夫に雰囲気が似ていた。ユフコは首を小さく横に振った。
兜は無い。血で固まった短髪。顔半分には血の跡。無精髭は無い。鎧は傷だらけ。足は草履。見慣れぬ旗印。どこの領国の出か解らない。遠い国から来たのだろう。「家まで案内いたします、薬と寝床があります」とユフコは気丈に云った。もはや彼女の心は決まっていた。
落武者は短い思案ののち、もう一度礼を云った。「かたじけない」と。彼は意識が朦朧としているようで、その足元は覚束ない。この思案にも、果たしてどれほどの意味があるのか、甚だ怪しいものだった。
ユフコは危険を承知で、肩を貸して歩いた。落武者の体は熱を帯びて熱く、鉄と硫黄の匂いがした。
ここから先は
この記事が気に入ったらチップで応援してみませんか?


