
【ワン・ガール、ワン・ボーイ】
◇総合目次 ◇エピソード一覧
この小説はTwitter連載時のログをそのままアーカイブしたものであり、誤字脱字などの修正は基本的に行っていません。このエピソードの加筆修正版は上の物理書籍に収録されています。第2部のコミカライズが、現在チャンピオンRED誌上で行われています。
1
フスマは微かに開いていた。部屋の明かりがついている。ウシミツ・アワー。彼女は隙間に顔を近づけ、中を覗く。父親はソファーに座っていた。彼女は血の気が引いた。父親は眠っていなかった。テレビもついていない。オーディオも。読書をしているわけでもない。ソファーにかけ、ただ、そこに居る。
父親はリビングのソファーにかけたまま、虚空を見つめている。時折、瞬きをしながら。「……」刺すような不安に心臓を締め付けられ、さりとて声を掛ける事もできず、彼女はフスマの前で凍りついていた。彼女のせいだ。当たり前だ。彼女のせいなのだ。平気なはずが、あるものか。
マッポのもとから帰ってきてからも、父親はあちこち電話をかけ、長く話していた。(お前は休んでいなさい。色んな事があったんだ)この日、遅い夕食をとったあと、父親は彼女の肩に手を置いて、優しく言った。(何も心配する事はない。お前は何も悪くない。お前は私と母さんの子なんだから)
父親は彫像めいて動かない。彼女は苦しく逡巡する。フスマを開け、大丈夫?と声をかけるか?そんなバカな……大丈夫な筈がないのだ。彼は優しく笑うだろう、そして、大丈夫だよ、と言うだろう、そして彼女は打ちひしがれるだろう。このまま、99%の予感を100%の真実にする事を拒みたい。
(クラスの皆はどうなった?)彼女は言葉を口にしようとした。どうなっただって?(皆は……)彼女は涙を流そうとした。涙は流れてくれなかった。乾いた目を何度も拳で拭った。(皆は……誰か、無事だった人は、いた?)父親は動かない。(死ななかった人は、いた?生きている人は?)
いない。彼女は自答した。いたとしても……。彼女は震えながら後ずさる。急に思い出したのだ。この翌日に起こる事を。このリビングで、彼女が見つけるものを。その後、彼女がやる事を。「嫌だ」彼女は呟いた。背後の闇を振り返った。「嫌だよ」答えはない。耳に返るのはズズズと唸る焦げ臭い空気だ。
「お父さん」彼女は力なく廊下に座り込む。「お父さん。死なないで。お父さん」リビングに入れない。入ればきっとそこは朝で、彼女は見る事になるだろう。「お父さん。死なないで」「死ぬんだよ」ゴウゴウと唸る炎の音が彼女を取り囲む。炎の中から囁き声が湧き出す。「死ぬんだよ。みんな死んだ」
「嫌だ」「死ぬんだ」「嫌だ!」「死んだじゃないか」「嫌だ!嫌だ!」炎が笑いながら彼女の周囲で渦を巻き、嘲った。炎の奥に、天井から吊りさがるロープが見えた。炎が悲しみを呑んだ。「アイエエエ!」悲鳴は彼女のものか。それともクラスのあいつらの断末魔か。それとも父親か。「アイエエエ!」
「アイエエエエ!」「アイエエエエ!」「アイエエエエ!」声!声!声!彼女は叫んだ。「助けて!助けて!助けて!」ターン!リビングのフスマが勢いよく開いた。バックドラフトじみた炎の奔流と共に、何かが……誰かが飛び出してきた。人影は彼女へタックルめいて飛びかかった。「イヤーッ!」
「アイエエエエ!」彼女はその者に抱えられ、炎の中から冷たい夜の外気の下へ飛び出した。KABOOM!後にした建物が爆発炎上した。「アイエエエ!」彼女は声をからして叫んだ。そしてその者にしがみついた。「アイエエエ!」「平気だ」その者は彼女の背中をさすりながら呟く。「もう平気。な」
「……!」嗚咽のせいで、言葉が出ない。「平気だ」男は繰り返した。「見ろよ。な。綺麗なもんだぜ。もう大丈夫だ」彼女は恐る恐る目を開いた。……そこは砂浜だった。銀色の砂に、暗い波が打ち寄せる。「泳いだっていいさ。アイスクリーム屋台は……あるかわからねえけど」男は言った。
彼女は我にかえり、身を離して立ち上がった。頭上の闇には金色の立方体が浮かび、ゆっくりと自転している。彼女はこめかみを押さえた。「アンタ……お前は……」「ああ、俺だ」男も砂を叩きながら立ち上がった。人の良さそうな笑みを浮かべた。「……」「あれ?アイサツした事、無かったか?」
「……」「ここは、アー、夢だ、夢じゃないんだが、夢だと思えばいいよ。さっきのも夢、アー、記憶……ニューロンのさ、ややこしいんだ、説明するのが」「……」彼女は両手を見下ろした。馴染みのある服、馴染みのあるマフラー、馴染みのある髪。「アタシだ」「ああそうだ。もう平気だよ」
「……」「いや、平気ッてのは、さっきまでの状態がもう無いって事。万事OKって事じゃないんだ。現実はそれはそれで相当ややこしいんだぜ。現実の俺たちは。アンタ……君はさっきの場所に閉じ込められていて、アー、多分、防衛反応だと思うんだ、でも自家中毒っていうかさ、マズくて……」
「見たのかよ」彼女は男を睨んだ。「いや、しょうがねえだろ!」男は制止の仕草をした。「賭けだったんだ。四の五の言えねえよ。君があのままじゃ、俺だってヤバイくなって……」「チッ」彼女は舌打ちし、掌の炎を握り消した。そして涙を拭った。彼女は驚きの表情を浮かべ、呟いた。「……涙だ」
01001001001010111彼女はフートンを跳ね除け、起き上がった。「グワーッ!」額を思い切り硬いものにぶつけ、苦痛に呻いた。狭い!まるでカンオケだ。「何だこの……」数秒間考え、状況を整理する。彼女はそこからズルズルと廊下へ這い出した。やはりだ。カンオケ・ホテルだ。
「ブエッ!」彼女はクシャミをし、頭を搔いた。掻く手が止まった。彼女は、眉……眉毛は永久脱毛され、代わりにイバラめいたタトゥーが施されている……眉根を寄せた。髪型に違和感を覚えたのだ。「何だ?」カンオケの中に残された荷物を掴み、「地獄お」と書かれたマフラーを首に巻いた。
「オイ」彼女は清掃作業中の店員に声をかけた。「便所どこ」「ハイヨロコンデー。あっちですね」清掃員が指差す先に彼女はドカドカと歩いてゆく。洗面台と曇った鏡に、彼女は対面する。「あン?」彼女は額に、前髪に手を当て、側頭部に手を当てた。「……あン?」彼女は顔をしかめた。
ショートボブ、黒髪の、痩せた女が鏡から彼女を見返す。「……ファック」彼女は呟いた。何らかの感情の動きに連動するかのように、頭頂部から毛先へ、炎めいた輝きが波打ち、髪色が真っ赤に変じた。彼女は荷物にしゃがんで、小さなハサミを見つけ出すと、前髪を生え際ぎりぎりで一直線に切断した。
◆◆◆
思い切りの悪かった前髪が、これで良い塩梅になった。彼女は鏡に向かって歯を剥き出した。状況はわかるようでわからない。イクサの記憶の断片と、ただ「なるべくしてなった」という実感めいた感覚がある。テックジャケットのポケットを探るが、ガムは無い。床の荷物を蹴り上げ、キャッチする。
「ここネオサイタマ?」彼女は呟いた。答えはない。蛇口の水を頭から被り、赤い髪を振り乱す。その後、ゴキゴキと首を鳴らし、廊下へ戻った。「ネオサイタマだよな」出口カウンターのチョウチン型精算機にトークンを投入した。キャバァーン!「マタヨロシクドーゾ」掃除スタッフが呟いた。
「アカチャン!どこまでもプカプカプカー、プ、カ」「驚くほど新しいバリキ!新型成分に注目重点!」「よくない……でもこれイイ!」「飛ぶ。そんな時代じゃないですか?」狭い階段を上がり、地上に出た彼女を、けたたましい広告音声とネオンの光が迎えた。電光板に時刻表示がある。19時だ。
「どうすッかな」彼女は歩き出しかけて、立ち止まり、遠い空を見やった。偶然それは西の方角だ。ネオサイタマからキョートへ。それからまたネオサイタマへ戻ってきた。戻ってきてから、何度か身を守った。炎で身を守った。漠然と覚えている。しかし、これではまるでウラシマ・ニンジャの伝説だ。
じき、あの銀色の砂浜に戻って、あの男をもう少し問い詰めないといけない。話は半分だ。彼女は拳でこめかみを叩く。何をするか……何から始めるか。「ハッケ!」「ハッケ!」ハッケ・プリーストの集団がストリートの人々にキアイを送る仕草をしながら練り歩く。彼女はその列を横断し、路地に入る。
路地にはボンボリじみた明かりを放つ電子据え置き看板が折り重なり、楽しげなアトモスフィアで彼女を誘う。「パターン派」「恐いゴス」「お経」「スポーツ音楽」……。看板の近くに、いくつか地下への階段がある。地下クラブ界隈だ。
彼女はそれらを通り過ぎる。その先で目ざとく見つけ出したのは、「音楽を聴くな」と威圧的に書かれた、ヒビ割れたガラスショドー看板だ。ゼン。モヒカン数人が気絶して寝そべる階段の下から、ズムズムとビート音が漏れ出てくる。彼女は躊躇せず降りて行った。
突き当りのスティールフスマには赤いスプレーで「壁」と書かれている。彼女はスティールフスマを引き開けた。「アーッ!王子!王子!ぜんぶ王子!おまえらが王子!バカ!」途端に強烈な音圧が彼女を真正面から捉え、赤い髪を揺らした。「王子!オスカーワイルド!お前ら王子!何もねえ!」
彼女は闇の中へ足を踏み入れる。狭いフロアにはパンクスが満載だ。彼らの叫びが、汗が、蒸気となり霧となって、ステージライトをコロイド粒子効果重点する。「アーッ!王子!王子!お前ら笑ってる!全部バカ!王子!アーッ!」
ステージ上でがなりたてているのは新鋭パンクバンド、「故障」。いわゆるケジメド・チルドレンのひとつで、文学的見地に立った個性的なアンタイセイ歌詞が話題となっている。「王子!アーッ!」もぎり男は泥酔している。彼女はそのままカウンターへ行き、サケを買う。
その時だ。「ウオー!」客の一人がステージによじ登り、ヴォーカリストを殴りつけた。マイクを奪って叫んだ。「オスカーワイルド曲解してんじゃねえ!」ベーシストは躊躇わずベースで乱入者を殴った。「グワーッ!」ゴゴゴゴー!ギターリストはアンプに頭を打ちつけながら、構わず弾き続ける。
「ファッキンハイプ!」更に一人!また一人!パンクスが次々に乱入!最初の乱入者はヴォーカリストと上になり下になり、マウントを取り合いながら殴り合いを始めた。「……」彼女はそれを目で追い、サケを一息に飲み干すと、グラスをカウンターに叩きつけた。そしてステージめがけ飛び出した。
「「ウオーッ!」」既に演奏を続けているのはトランス状態のギターリストだけだ。ドラマーはタムを蹴ってダイブし、タイキスト(太鼓叩き)は太鼓を持ち上げようとしたがかなわず、悪戦苦闘している。「アンタイセイ同士が!」彼女はヴォーカルを殴った。「グワーッ!」「揉め事してんじゃねえ!」
「ウオーッ!」パンクスの一人が彼女に殴りかかる!「イヤーッ!」彼女は振り返りざまの左裏拳を顔面に叩き込んだ。「グワーッ!」「イヤーッ!」更に右ストレート!「グワーッ!」パンクスは白目を剥いて吹き飛ぶ!「イヤーッ!」後ろ回し蹴り!別のパンクスを直撃!「グワーッ!」
ゴウ!ゴウ!闇の中で火の粉が閃き、彼女の獰猛な目が輝いた。その両肘が溶けた鉄のように赤熱し、ジェットじみて熱を吹きはじめる。「ウオーッ!」「ウオーッ!」ステージ上は人だかり!暴動だ!彼女は笑い出した。飛んできたスネアドラムを、彼女は殴り飛ばした。スネアドラムが弾け飛んだ!
弾け飛んだスネアドラムの金具は周囲のパンクスに火山弾めいて降り注ぐ!「グワーッ!」「熱ちッ!」「熱い!」「グワーッ!」「ウオーッ!」「ウオーッ!」「マッポだ!マッポ来たぞ!」「御用!」「マッポだ!」「逃げろ!」「ポルカを踊れ!」「逃げろ!」どよめきが人々を伝搬する!
「上等だよ!」彼女は燃える目を見開き、火の粉を宙に散らしながら笑い叫んだ。「消し炭にしてやらァ!」入り口から突入してくるマッポ隊めがけ、彼女は跳んだ。その踵は溶けた鉄めいて赤熱し、ジェットを吹いている。不可思議なカトン・ジツ応用である。「イイイイイヤアーッ!」
彼女は恐るべき悪竜めいて襲いかかろうとした。光り輝く赤い髪が、しかし、そのとき突然に黒く変色し、彼女は今まさに踏み込んできたマッポの目の前におとなしく着地していたのだ。黒髪には再び炎が波打ち、髪色は赤に戻った。「……あン?」彼女は呆けたように、己の手の平を見た。
その直後、ポルカが流れだした。機転を利かせたDJのしわざだ。ホールはやや明るくなり、パンクス達は互いに睨み合いながら、ポルカを踊り始めた。「……」彼女は立ち上がり、踊るパンクス達と、目の前で警棒を弄ぶマッポを見た。「オーナー!責任者!」マッポは苛立たしげに叫んだ。
「アッハイ、私です、ハイ」揉み手をしながら、2メートル近い巨漢が現れた。「お勤めご苦労さまです」「近隣の通報だぞ」マッポはオーナーの胸を警棒でトントンと叩いた。「留置場に全員入れてもいい!」「見ての通り、暴動なんかありません。ポルカの集いでして」オーナーはホールを仰ぎ見た。
「チィーッ……」マッポリーダーは悔しげにパンクスを眺めた。「あいつは何だ!口から血を流している」「ウルッセェー!転んだんだよ!」パンクスが踊りながら叫び返した。「ポルカしてて転んだんだよ!」「チィーッ……」マッポリーダーは部下数人と視線を交わす。証拠がなければ摘発はできない。
「わかりましたか?あとこれ、客の忘れ物なんで。持ち主探してください」オーナーはフロシキ包みを差し出した。賄賂だ!マッポリーダーの表情が動いた。彼はフロシキ包みをひったくるように受け取ると、「いつでも摘発できることを忘れるな!」言い残して、出て行った。
マッポが去ると、即座にポルカはスカに引き継がれた。パンクスはスカダンスを開始し、肘と背中で互いに押し合い、脛を蹴りはじめた。「……アー……」彼女は口を開けてそれを見た。「マッポ乱入もピリッと効いたアクセントになったろうが。嬢ちゃん」オーナーが彼女の肩を叩いた。
「アー」「名前何てンだ。目立ってたぜ。やるじゃねえかよ。腕っ節もいい」オーナーは笑った。「名前」彼女は名乗ろうとして、やはり、やめた。妙に気が引けた。問題が片付いていない。現状も把握できていない。彼女は咄嗟に名乗った。「ブレイズだ。ブレイズにしとく」「何だそりゃ?」
「いいンだよ!」彼女は胸を張った。そして言った。「やるじゃねえかのついでに、一杯おごってくれよ」「フーム、フム」オーナーはバーテンにスピリットを用意させた。「見かけねえな。初めて来たのか」「そう」「どこから来た?」「アー」彼女は頭を掻いた。「立て込んでンだ。今度訊いとくよ」
2
「だいたいわかった」ブレイズはしかめ面でイカケバブに噛りついた。「……味しねェ」砂浜に放り捨てると、0と1の銀色の砂飛沫とイカが溶け合い、消失した。「だから言っただろ」銀色の影めいたニンジャは焚き火の向こうでアグラした。「味の再現は難しいんだ」「じゃあ、無理して作ンなよ」
「やってみたかったんだよ」ニンジャは言った。「何かこう……文明的なものがあってもいいかなッてな!」「イカが文明?」ブレイズは遠くの屋台を見やり、呆れたように首を振った。話を戻した。「ギルド、なくなっちまったのな」「そういう事になるな」ニンジャは答えた。「イクサだ」
「せいせいするぜ」ブレイズはツバを吐いた。「……」ニンジャは彼女を見た。ブレイズは肩をすくめ、「アタシをコケにしやがったからな。世話になった奴も、もうあんまり残ってねェし」「そうか」ニンジャは言った。「双子のニンジャと知り合いだろ」「アンバサダー=サンか?」「今はキョートだ」
「ふうん」ブレイズは暗い海を見ながら、「フェイタル=サンは?」「アー……あいつもそうか」ニンジャは呟き、「生きてるんじゃねえかな……」「大ッ嫌いだったんだよ、あのネエちゃん!」ブレイズは吐き真似をした。「まあイイさ。とにかく、まとめると、まずは寝るところの確保だろ?」「だな」
ニンジャは身じろぎした。「後は、長期的目標だ」「……」ブレイズは溜息を吐いた。「アンタが、こッから出て行く」「そうだ」ニンジャは頷いた。「あのさ……実際その……」言いかけるのをブレイズは制し、立ち上がった。「しょうがねェ事だったンだろ?」「まあな」「じゃあ、しょうがねェだろ!」
ブレイズは無造作に砂を蹴り、「こンだけ顔突き合わせる奴に、いちいち同じ文句垂れてられッかよ!だけど、方法がわかったら、とっとと出て行けよ!」「そりゃそうさ!その方法がわからねえってのが問題だけど……」銀色のニンジャは言った。「どうにかするさ。ギンカクとか……色々調べる事はある」
「なんで、さっきアタシを止めた?」ブレイズが銀色のニンジャを振り返った。「止めたって?」「止めたろ!アタシのカトンを!」「アー」銀色のニンジャは頷いた。ニンジャは敵対者を殺傷する事に殆ど躊躇を覚えない。彼とてもそうだ。だが、「何かヤバイと思ったら、止まったな……」「アア?」
「いや、俺だってそうホイホイ自由に君と入れ替わったりできるわけじゃねえさ。説明したろ、その辺は!だから、俺のせいではあるけど、直感的な、無意識の介入なんだよ、わかんねえよ!」「ファック!」0100101011101……「オイ!起きてくれよ、店閉めるよ」
ブレイズはカウンターに突っ伏して寝ている己を認識した。バネ仕掛けめいて跳ね起きると、床をモップ清掃していたダブルモヒカンスタッフが押されて転倒した。ホールに明かりがついている。朝4時だ。既に他の客の姿はない。「ア?終わり?」「おう」オーナーが笑いかけた。「ガキみてえに寝てたな」
「また来るよ。アタシ、ヒマだし」ブレイズは頭を掻いた。オーナーは頷いた。「来週で閉店だけどな」「閉店?ナンデ?」「ここ最近、締めつけが厳しくなった。今回もあったろ。マッポの乱入がよ」「マッポ?最近?」「ヤッコ法とかいうやつだよ」ダブルモヒカンスタッフが横から言った。
「5人以上の人間が深夜に集まる時は事前に届けが要るんだとよ。ファックオフ!」ダブルモヒカンスタッフはキツネサインした。オーナーは言う。「くされ法律だ。まだ本決まりになってねえが、マッポは今からあれこれ難癖つけて来てやがる。目をつけられちまったら、さすがに続けてられねえ」
「ウェー」ブレイズは顔をしかめた。「何だそりゃ。しょうもねェな」「どッか他を探すこッたな。俺は歳だし、隠居だ」オーナーはブレイズの肩を叩いた。「そのかわり、来週の最後のマツリは来て後悔しねえぞ、ウチにゆかりのある連中が集まるからな!」
「アベ一休だぜ!」ダブルモヒカンスタッフが言った。「マジなんだぜ!」「アベ一休?」ブレイズは首を傾げる。「ア?何で今更?だいたいシゲキの替わりは……」「シゲキの弟がやるんだ。14才。少年院から出所した」「弟?」「アベ一休だけじゃない。タケシも来るかもしれないんだ」「タケシ!」
タケシはハードコア・ヤクザパンクバンド「ケジメド」のヴォーカリストだ。中指以外をケジメした彼は、いわばパンクのリヴィング・レジェンドであったが……「失踪したッきりかと思ってたけど、戻ってきたの?そんな事になってたのか」「いや……はっきりしねえんだけどさ。目撃情報が多いんだ!」
ダブルモヒカンスタッフは勢い込んだ。「ケジメドと『壁』は切っても切り離せねえ……もしタケシが生きてるなら、絶対来る筈さ。終わりを見届けにさ!」「ウェー」ブレイズは驚きの唸り声を発した。「いいタイミングで目が覚めたンだな」「そう、閉店時間だ」オーナーが勘違いして相づちを打った。
◆◆◆
「ヒートリー、コマキタネー……」「ジミーのメソッドだ」「ちまき」夜のキバレ・ストリートは昼の三倍煩い。繁華街ネオン、ポン引き、オイラン看板……この区域のパトロールを行うマッポは特に警戒が厚い。スリーマンセルを組み、本格的な武装でマッポガン強奪、警察手帳強奪事案への備えとする。
「ブフーッ。オゲーッ」三人の真ん中、ゲップをしつこく繰り返す太ったマッポは、その武装のみならず、トゲつき制帽、はだけたシャツからのぞく胸毛、どろりと濁った悪意の塊めいた眼差し、全てにおいて危険人物のアトモスフィアを隠しもしない。
両サイドの二人は通行人に厳しい目線を送りながら、時折凶悪マッポを振り返っては、卑屈な笑いを向ける。チャラリラッパパパオー……パチンコ店の開閉自動ドアから一定間隔で吐き出されるアタリアラーム音。凶悪マッポは分厚い唇をずらした。「オイ。あいつな」指差す先にはチョンマゲギーク青年。
「ヨロコンデー!」二人は素早く頷き、一切の淀みない動作でチョンマゲギーク青年の両腕を左右からガッチリとロックした。「アイエエエ!」「ブフーッ」凶悪マッポは警棒を手の平に打ちつけて笑う。チョンマゲギーク青年は両脇のマッポを交互に見た。「あのう、何ですか?」「何ですかじゃねェー」
「お前、我々を見てビクッと……怯えたな?」凶悪マッポはガムを口からつまみ取り、震えるチョンマゲギークの眉間に押しつけた。「アイエエエ!そんな……」「やましい事があるから怯えるんだ。エエッ?俺たちは市民の味方だ……何で怯えてやがる。絶対怪しいぜ。なあ」「本当ですよね!」「ね!」
「僕は何もしてないです!」「何もしてないだァー?」凶悪マッポは睨みつけた。「そんな質問してねえだろ?何か悪さしたか、とか、質問したか?してねえのにそんな……自発的にハキハキと……まさかお前、物騒な事考えてんのか?怪しいぜ」「本当ですよね!」「ね!」
通行人は質問光景を一瞥しては、足早に通り過ぎる。恐怖と恥辱に、チョンマゲギーク青年は青ざめる。通過する者の中には、スモトリ崩れのタフなギャング集団もいた。四人組の彼ら全員が抜き身のカタナを二刀流で威圧的に構えている。マッポ三人はそれを無視。ギークに集中する。
「ネエチャン!前後させろ!」「アイエエエ!」道ゆくオイランをスモトリギャングがカタナで脅す。悲鳴をあげて逃げてゆくのを、ギャング集団は下卑た笑いで見送る。一部始終をマッポは完全無視!チョンマゲギークを小突き、「カバンの中身、路上に全部並べろ。キッチリ並べろ」「アイエエエ!」
ギーク青年は嗚咽しながら、「何の権利があって……」「我々には市民生活を守る義務がある!」凶悪マッポは遮り、「やましくないなら出来るだろ?だいたい、お前みたいな陰気な奴が一番危ない!サイコの温床だ!わかってんのか?コラッ!」「本当ですよね!」「ね!」「アイエエエ!」
泣きながらノート類や文房具を並べるチョンマゲギークを侮蔑的に見下ろし、凶悪マッポは他の二人に言う。「こうやってキリキリやるんだ。な?ガンガンパトロールポイントが溜まって、出世街道!」たくましい毛むくじゃらの二の腕を見せつける。「ありがたく学べよ!」下劣会話を隠しもしない!
チョンマゲギークがカバンの中身を並べ終えると、凶悪マッポはそれをスパイク革靴で踏みにじり、身分証明のコピーを取った。「異常なァーし。協力ご苦労!」そして再び歩き出す。二人のマッポが薄笑いを浮かべて続く。ギーク青年は道路にうずくまり、震えて動かない。
ナムアミダブツ……何たる横暴!だが、彼のゆくところ、この手の行いはチャメシ・インシデントなのだ。彼こそは凶悪マッポの旨味を知り尽くした男にして、実はニンジャでもある。裏の名をキングピンと言う!翌月に配置転換を控え、その悪事はますます過剰であった!
「あのギーク野郎、ドライバーか何か持ってりゃもっと楽しめたのに」取り巻きの一人が振り返り振り返り言った。「それか、マンガとか。なんだよ、ノートって。最悪のマジメ野郎だな。空気読めってんですよ」「ゲエエエップ」キングピンは耳をほじりながらゲップをし、放屁で答えた。脇道へ入る。
うらぶれた通りにはスキンヘッドの小柄な男が立ち、卑屈な目でキングピン一行を見た。彼の隣には「グッド娘さん」と書かれたピンクの看板がある。「ドーモ。キングピン=サン!」小柄な男は深々とオジギした。そして恭しく封筒を差し出した。「今月分です!」
「まじめに働いてるか?遵法してるか?エエッ?……エート、何だっけかなァ、名前は」キングピンは一枚一枚、指を舐めながら万札を数える。「シャマコだ。シャマコ」「大人気ですよ。おかげさんで」「当たり前だ」キングピンは歯を剥きだして笑った。「目利きだぞ、俺は」「本当にそうです!」
「シャマコはもうすぐ人気一位です」「磨けば光る。そういう女をモノにすンだよ。わかるか?」キングピンは取り巻きを振り返る。そして再び女衒を見る。「こいつらが、俺のかわりに今度から仕切るからな。支店長と支店長補佐だ。グフフ。わかったか」「ハイ!」女衒が再オジギする。
女衒と取り巻き二人が名刺を交換するのを尻目に、キングピンは階段を上がってゆく。「楽しんでください!」女衒が声をかけた。ナムアミダブツ……この店で奉仕するオイラン達は、キングピンが強引に逮捕・保護し、弱みを握った女達だ。このやり口は、彼のメイン・ビジネスの一つである。
配置転換のたび、彼は抜け目なく、手下マッポを「支店長」として、己の息のかかった暗黒店舗の管理を引き継がせてきた。ネオサイタマ各所から彼の口座へ、不労所得が毎月振り込まれてくるという寸法だ。彼はニンジャであるが、暴力は余程の事がなければ必要としなかった。マッポ権力があるからだ。
マッポ権力といっても、彼の「わきまえ方」は非常に注意深く、彼なりの一線を保ったものである。支配と言うにはいかにも卑しい小悪党じみたビジネスであり、それが彼の独特の立ち位置を築いている。だが、そのビジネスの踏みつけになり、ジゴクを見せられる市民の数たるや……ニンジャの所業!
「もっとシバきあげてやりてえぜ……どこかねェか……スカッとするような……」警棒を手の平で弄びながら、キングピンはゆっくりと階段を上がる。「いい街だったぜ、寂しくなるぜ……いけすかねえガキ共、タフガイ気取りの奴ら……反抗的な奴ら……せっかくだから楽しまねえとな……グフフ……!」
キングピンの到着を足音で察したオイラン達は、それぞれの小部屋のショウジ戸の向こうで一斉に身を固くする。邪悪なマッポニンジャはニンジャ聴力でその様を知覚し、下卑た笑みを浮かべた。「どいつにするかな……」彼は足を止めた。ショウジ戸には「ビワヨ:パンクス風、美的」と書かれている。
「パンクス……」彼の邪悪なニューロンにインスピレーションが閃いた。「昨晩アホどもが摘発しそこねた店があったな、パンク野郎の……グフフ、クズガキ共をギタギタにしてやるか……見せつけてやるか!大人の権力を!」ターン!勢い良くショウジ戸を引き開けた!「アイエエ!」「楽しくなるぞ!」
3
「アーッ01011ザリザリ……未来は無い!未来…101101ザリザリ……」ノイズまみれのサウンドを吐き出すIRCラジカセを、ブレイズは拳で殴りつける。ラジカセは壊れて動かなくなった。「な?なかなか難しいんだよ」鈍い銀色のニンジャはイカを齧りながら言った。
「ローカルコトダマ空間ってのは、潜在意識だから、自分で意図したものを作るっていうのは大変なんだ。その人にとっての、ある種の切実さ……強烈な記憶の焼きつき……そういうものが大事なんだな」彼は焚き火越しにもう一つのイカを差し出した。「イカはもう、だいぶいいよ」
彼女はそれを受け取り、咀嚼した。「……まあね」「パンクが好きなんだな」ニンジャは言った。「どんなとこが良いんだ?」「ア?」彼女はイカを噛みながら、ニンジャを睨んだ。「……顔かな」抑揚のない声で答える。「顔?」「だいたい、フロントマンの顔がカワイイ」「顔なのか」「悪いかよ」
「見た目……生き方じゃないのか?」「生き方ッてのは、見た目だろ」「でも、スモトリパンクスとかは」「そういうのは、お呼びじゃねえな」彼女は火の中に焼き串を放り込む。砂を叩いて立ち上がり、頭上で自転する黄金の立方体に向かって叫んだ。「起こせ!」……どこからかアラームが聴こえてきた。
「オゴーッ!」サウンドチェックのステージ上、サンダンウチのヴォーカリストが嘔吐した。メンバーである三人のギターリストは激昂し、ヴォーカリストを蹴ったり、ギターで殴ったりした。「バカ!」「汚ねえんだよ!」ダブルモヒカンスタッフがモップを投げ、「自分で掃除してよね!」と叫んだ。
「後がつかえてンだよ!ちゃんとやれ!」サウンド・エンジニアがブースから怒鳴りあげた。エンジニアの権力は絶対だ。ナメた真似をして、演奏中に音を消されても文句を言えない。ギターリストの一人がモップがけをしながら、うずくまるヴォーカリストを踏みつけた。「こいつ深酒しちまったンだよォ」
「今夜はよォ……アベ一休……オミソ……もしかしたらタケシ……すげえ。何が起こるかわからねェ」ヴォーカリストは、えづきながら起き上がる。「だからナメられるわけにはいかねェんだよ!キメてこねえとよ!」「二日酔いで使い物にならねえんじゃ世話ねえな」エンジニアは冷たくコメントした。
そうした様を、ブレイズは、階段の脇にしゃがみこんで眺めている。アクビを噛み殺し、耳をほじった。「正直こんなもん見たくねェんだけど!」ステージ上で殴り合いを始めたサンダンウチから目をそらし、ダブルモヒカンにぼやいた。「遅刻してくりゃよかったぜ」「そう言わずに。早期警戒が大事」
ダブルモヒカンはしたり顔で言った。「こういう開演前の準備時間は、客がいない、つまり、頭数が少ないでしょ?そういうところを狙われたりするんだよ。マッポならまだしも、ロカビリーやナショナリストが大勢で攻めてくる事もあるぜ。火炎瓶事件知ってる?」「とにかくブン殴ればいいんだろ」
「ちゃんと考えてよ。正当防衛でも、やり過ぎたらマッポにアレされるし……」ダブルモヒカンは言った。「アンタはどうか知らないけど、少なくとも俺やオーナーは、ムショには入りたくない類いのパンクスなんだ」「アタシがそんなバカに見えるかよ?」ブレイズは不服げに言った。
彼女は先日の乱闘騒ぎの度胸を買われ、なりゆきでこのライブハウス「壁」の臨時セキュリティとして雇われていた。「壁」はこの日をもって閉店となるが、鈍色のニンジャと入れ替わる形で突如ネオサイタマに投げ出され、収入のあてのない彼女にとってみれば、渡りに船の臨時収入源だ。
「オーナーは隠居、アンタは失業?」ブレイズが尋ねる。「そう」ダブルモヒカンは頷いた。「俺、マジメだからね。失業保険がもらえる。今、どんどん給付基準が厳しくなって来てるけど」「フーン」「貯金もしてるからね。俺、堅実だから」「フーン」「心に決めてる事があるんだよね」「フーン。何」
「ヨタモノ知ってるでしょ。あったでしょ、ムコウミズのヨタモノ」「アー。ライブハウスか。燃えただろ」「そう」ダブルモヒカンは目を輝かせた。「聖地でしょ?やっぱり。あんな終わり方ないよ。すごい沢山パンクスが死んでさ。よくないよ。……で、どうにかしたくッてさ。復活させたいのね」
「復活ねェー……」ブレイズは頭を掻いた。ダブルモヒカンは勢い込んだ。「俺はもともとヨタモノに入り浸ってたワケ。だからね、これ、悲願ね。俺一人じゃそりゃあ、無理だよ。まだまだ無理。でも、有志をつのってさァ。心意気をさァ……」「オイ!こっち、どうなってる!」オーナーが彼を呼んだ。
「ハイヨロコンデー!」ダブルモヒカンはブレイズににっこり笑い、駆け去っていった。ステージ上では次のバンド、故障のメンバーが、サンダンウチと剣呑な視線を交わしている。ブレイズは所在なく、階段を上がって裏口から出ると、壁に寄りかかって座った。「ブエッ!」光が差し、クシャミを促す。
「ここ、壁?」「あン?」ブレイズは声をかけてきた男を見上げた。ガリガリに痩せた男が彼女を見下ろす。逆光の中、落ち窪んだ目、眉間の深い皺、デコボコの短髪。「コシャクな」と書かれたTシャツを着ている。首周りはほつれてボロボロだ。「ここ、壁?」「アベ……!」ブレイズは息を呑んだ。
「壁?」「壁?壁だ」ブレイズは慌てて立ち上がった。男は三白眼でブレイズをじっと見た。「俺……アベ一休……歌ってる」「知ってるよ」ブレイズは小さく呟き、マフラーを鼻先まで引き上げた。「入れるよ。入れよ」「俺……俺、だいたい早い。来るの、早い」ブレイズは頷き、階段を無言で指さす。
「ドーモ」男は……伝説的パンク・バンド、アベ一休のヴォーカリスト、ユシミは、フラフラと階段を降りてゆく。「ユシミ=サン」ブレイズはその背中に声をかけた。「タイコ……シゲキのかわりは」ユシミが足を止めた。「うん、弟、シゲキ、弟、シゲキ」彼はブツブツと呟いた。「死んだシゲキ」
ブレイズは言葉を探したが、ユシミはそのまま降りていった。マフラーの下で彼女は唸り声を押し殺した。……「ここ、壁ッスよね?」「ア?」かけられた声に我に返り、彼女は振り返った。「当日券無いッスか?」「知らねえよ!」彼女が邪険に睨みつけると、パンクスはツバを吐いて去っていった。
ゴゴゴウン。ゴゴゴウン。下からは「故障」の鳴らすギターの轟音が漏れ聞こえてくる。ユシミはフロアに立って、その様子を見ているのだろうか。それとも楽屋で寝るだろうか。ブレイズはとりとめもなく考えた。ずるずると壁を背中がすべり、彼女は再び座り込んだ。彼女はずっと考えていた。
◆◆◆
最初のバンドの登場を待たずして、既に「壁」の動員数はキャパシティ限度に達しようとしていた。フリークアウトしたパンクスが何人かの友人に抱えられて階段を運ばれてゆく。「先走って盛り上がり過ぎだな」ダブルモヒカンスタッフが辛辣にコメントした。「アー」ブレイズは上の空で呟いた。
「なに」ダブルモヒカンは入場者のチケットをもぎりながら、ブレイズを見た。「どうしたの。お腹空いたの。オニギリあるよ」「いらねえよ。元気だよ」「オニギリいらないの」「アタシ、アベ一休、活動中もそんなに入れ込んで無かったんだけどさあ」「アベ一休どうしたの」
「アタシが裏口の外に居た時、ユシミが入って来てさあ」「ああ。スゴイよね」ダブルモヒカンは頷いた。「ユシミはヤバイだよね。流石だよね」「パッと見、自我科患者みたいだと思ったんだけどさあ、違うんだよな……覚めてんだよな、それがさあ」ブレイズは呟いた。「それがさあ」「ベタ惚れだ」
「アー」「でもさあ、アンタ、担当は力仕事なんだから、頼むぜ、ヨージンボーだぜ」「アー、そうねェー」「ヨージンボー」「そうねェー」ドジャーン!その時である、ファーストバンドである「キリクチ・マゴ」のドラマーが背後の銅鑼を力任せに打ち鳴らし、縒れた下手なギターがビートに追随した。
「スゴイ!スゴイスゴイ寒い!フンフンフフーンなにか!フンフンフフーンなにかスゴイ!……キモチ!」ヘナヘナのギターを鳴らしながら、ボンズヘアー青年がマイクに食らいつく。「キモチ!フンフンフフーンスゴイなにかー!」ブレイクだ!だが全てのタイミングが少しずつズレている。
「キモチ!キモチパンク!」「キモチパンク!」「キモチパンク!」「ウオオーッ!バカ!」客の誰かが叫び、ケモビールの瓶を投げた。フロントマンは危うくこれをかわし、演奏を継続した。二曲目だ。「フンフンフフーンスゴイ!フンフンフフーンスゴイ!この街…」「カエレ!バカ!」「ウオーッ!」
既に客の何人かがステージによじ登り、乱闘を開始!具体性に欠ける歌詞はロマン主義的であり、ブルシットとされる。キリクチ・マゴは歴史あるこのライブハウスの住人に拒絶された!「ウオーッ!」「グワーッ!」誰かが殴られた。「ちょっと」ダブルモヒカンがブレイズの腕を揺すった。
「イイよ、まだ!」ブレイズはダブルモヒカンを振り払い、腕組みして言う「あんなもん、黙って見ててもしょうがねェだろ。あっためようぜ!」「あんまりアレすると、マッポが……」「まだ平気だよ!」ブレイズは歯をむきだし、「それに、そン時がアタシの出番だろ!アー、出て来たぞ、次の奴ら」
ブレイズは指さした。キリクチ・マゴはいまだかろうじて演奏を続けていたが、乱入者は容赦なく銅鑼を横から連続で打ち鳴らした。ドジャーン!ドジャーン!ドジャーン!ドジャーン!キリクチ・マゴのメンバーは観客と殴りあいながら、徐々にホールへ引き摺り下ろされ、ピットに呑み込まれていった。
「次は?サンダンウチだよな……あれ……?」ブレイズは背伸びして、眉根を寄せる。「サンダンウチじゃねえのかな?」ドジャーン!ドジャーン!ドジャーン!ドジャーン!丸刈りの男は銅鑼を鳴らし続ける。「あいつは違うな」とダブルモヒカン。「あいつ……」「シゲキ……弟!」ブレイズは呻いた。
ドジャーン!ドジャーン!仏頂面で銅鑼を鳴らし続ける男に、ダブルモヒカンは目を凝らす。「似てる気もするけど……アイエッ!」その顔のすぐ横を、飛来したプラスチック・グラスが通過した。「ウオオーッ!」「ウオオーッ!」客同士の乱闘はいつしかステージへの怒号、歓声に変わりつつあった。
叫び、手をたたき、チャントを繰り返す者らに混じって、ボソボソと呟かれる会話。「サンダンウチじゃないよ」「シゲキだ」「シゲキ生き返った?」「まだガキだよ……」「あれが弟だよ!」「出所!」「サンダンウチじゃないの?」「オイ!オイあれ……」ドジャーン!ドジャーン!歓声が静まり返る。
いつのまにか、ステージには痩せて背の高い男が立ち尽くしていた。デコボコの短髪、上半身は裸、瞬きを繰り返し、客を見渡す、困惑しているかのように。「ユシミ……!」誰かが震え声で呟いた。ゴロゴロ……そのときステージ袖から転がってきたのは、太鼓である。新たな三人が押して転がしている。
太鼓を転がしてきた三人のうち、一人はアンプに素早く白インクで<無垢>とショドーし、電子オコトをジャックインした。恐ろしくささくれだった電子ノイズが耳をつんざく。一人はベースを。一人はドラム。そしてシゲキの弟が遂に銅鑼を叩きやめ、太鼓にスタンバイした。ユシミがマイクを掴んだ。
「……」ユシミは口を開け、そのまま停止した。三白眼がせわしなく動いた。一瞬ごとに、客の一人ひとりの顔を捉えていた。「ア……」客の誰かがこらえきれず、叫んだ。「アンタイセイ!」すると、堰を切ったように、全ての客が吠え声をあげた。「「「アンタイセイ!」」」ドォン!太鼓!
ドォン!ドォン!シゲキ弟は仏頂面で太鼓を叩き続ける。緊張しているのだ!そこへドラム・ビートが重なる。更に、新規加入したとおぼしきベーシストの、歪んだ金属的サウンド!「「アンタイセイ!」」客の叫び!ユシミは突如、背をぴんと伸ばし、叫ぶ!それらの音をかき消す!「アンタイセイ!」
アンタイセイ!ANTI(アンタイ)とTAISEI(体制)を合体させたアベ一休の造語である!そして、ゴギギギギギガガガガガガ!恐るべき金切りオコト・サウンドが鼓膜に襲いかかる!ユシミは目を見開き、叫び始める。メロディーのかけらもない歌詞を。「止まったら!死ぬ!だから俺は死体!」
「アベ一休?」ダブルモヒカンが驚愕した。「もっと後だろ、ナンデ……まさか太鼓が14歳だから、深夜になる前に……?アーッ!ブレイズ=サン!ちょっと!」彼はもはやピットに消えてゆく彼女の背中を見送ることしかできない!「止まったら!死ぬ!だから俺は死体!動けねえ死体!殺された!」
嵐の海で空中に弾き飛ばされるバイオマンボウめいて、下から押し上げられた観客が酒の飛沫とともに乱舞する。ユシミはカッと見開いた目を一切瞬きさせることなく、怒りの一歩手前で強張らせた無表情で叫び続ける。「コンベア動くのを待ってる!止まったら死ぬ!だから死体!待ってる俺は死体!」
「止まったら死ぬ!止まってる!止まったら死ぬ!止まってる!」「俺は死体!」「止まった!」「止まったから死んだ!」「止まった!」「止まったから死んだ!」「止まった!」「曲は終わりだ!」ゴー……電子オコトのフィードバック音が等比級数的に大きくなる中、ユシミは床に仰向けに倒れた。
ドォン!ドォン!太鼓が心音めいて繰り返し鳴らされる。観客は固唾を飲んで次の曲を待つ。2曲やるかもしれない。今日は特別な夜。3曲やる可能性すらある!「アンタイセイー」最前列でガードバーに寄りかかり、感極まって嗚咽するのはブレイズだった。「アンタイセイー」……BLAM!その時だ。
BLAMBLAM!天井へ更に二度の発砲。更に、パオーウー!手回しサイレンが響き渡る。パンクスは前へ前へと詰めかけ、出口付近はがらんと空いていた。そこにマッポ達が展開した。皆が振り返った。パオーウー!パオ……マッポが手回しサイレンを止めた。チーフマッポが下卑た笑いを浮かべた。
「ゲエエップ!これはいかんなァー」チーフマッポはアンコドーナツを咀嚼し、チュッチュッとせせり音を立てる。パンクスの剣呑な視線を一身に集め、彼はなお平然としていた。ドォン……心持ち、太鼓の音が弱まる。シゲキ弟は仏頂面に脂汗を垂らし、床に寝そべるユシミを見た。ユシミは動かない。
「多分、全員薬物影響下にあるな、これは!逮捕は免れんなァー」チーフマッポが言った。「ちょっと待ってくださいよ、グワーッ!」進み出ようとしたダブルモヒカンはいきなり警棒で殴られ、床を這った。「正当防衛で殺害しなかっただけありがたく思えェーイ」チーフマッポは腹を掻く。
「何やってんだ……令状あるんですか」スタッフルームからオーナーが出てきた。「届けも出してる。違法性は無い……」「ダマラッシェー!」チーフマッポが吠えた。「「「アイエエエ!」」」半径10フィートのパンクスが雷に打たれたように恐怖に打たれ、後ずさった。「令状?寝ぼけた事抜かすな」
チーフマッポは警棒を手の平に打ちつけながら、「要は、俺が気に食わねえからイジメる。それだけだ、ガキども。理由は後で考えてやるから安心しろ。気に食わんガキをイジメる!それが大人の権利だ!その為に法律がある!俺はなんでもできる!俺は権力だぞ!」ナムサン!何たる開き直りか!
ホールは静まり返った。パンクスは互いに目を見交わす。オーナーは何か言おうとした。チーフマッポは素早く銃を向け、撃鉄を起こす。「アイエッ!」気の弱い何人かのパンクスが悲鳴を漏らす。「跪け。ドゲザだ」とチーフ。……「弟ッ!」その時、ステージ方向から怒声が飛んだ。
全員がステージ方向を見た。「手を!止めてんじゃねえ!」ふたたび、怒声。「え」シゲキ弟はツバを飲み、声の主を……床に寝そべったままのユシミを見た。「手を!止めてんじゃねえ!」みたびの怒声!「アイエッ!」シゲキ弟は怯み、歯を食いしばり、決死の表情で、太鼓を殴りつけた。ドォン!
「何を……」ドォン!ドォン!「やっておるかーッ!」チーフマッポは拳銃でシゲキ弟を狙う!引き金を引く!POW!銃口からは火の粉の塊が飛び、空中で散って消えた。チーフマッポは再び引き金を引いた。POW!銃口はクシャミめいて火の粉を噴きだした。更に引き金!POW!銃口が赤く溶けた。
ユシミは跳ね起きて、マイクを再び掴んでいた。「アン!タイ!セイ!」ユシミが叫んだ。チーフマッポは高速思考。銃口が溶けた理由を探る。彼のニンジャ判断力は一瞬で答えを導き出した。今、彼の顔面にジャンプパンチを……赤熱する拳を叩きつけようとしている赤髪の女に、やられたのか。
「こいつ、ニンジャ?」彼の血中をニンジャアドレナリンが駆け巡り、時間感覚が泥めいて鈍化する。赤熱する拳が迫る。パンチを繰り出す彼女の肘は、ジャケットを焼きながら、ロケットエンジンめいた火を吹いている。拳が鼻面にめり込んだ。「ニンジャ、ナンデ?」拳は彼の予想よりも二倍速かった。
4
「痛て……」チーフマッポの顔が変形してゆく。頬がへこみ、鼻が歪み、厚ぼったいくちびるが歪み、涎と鼻血が噴き出す。「痛てえ、ェェーッ!」拳は容赦なくチーフマッポにカラテ衝撃を注ぎ込んだ。「グワーッ!」チーフマッポはキリモミ回転しながら吹き飛び、尻をブレイズに向けて突っ伏した!
血飛沫はブレイズの体に付着する寸前で音を立てて蒸発。彼女は威嚇的に歯をむきだし、チーフマッポの尻めがけ突き進む。「イヤーッ!」ケリ・キック!「グワーッ!」尻を蹴られたチーフマッポは一回転前転!壁に叩きつけられる!「グワーッ!」「ファック!」ブレイズはキツネサイン!「オフ!」
「何しやがる!」チーフマッポは喚いた。「俺は公僕だぞ!」「強制執行重点!」他のマッポ達が警棒を構えた。パンクス達が一斉に襲いかかった。「アンタイセーイ!」ステージ上ではユシミが目を向き、再度の絶叫!ドラムロール!そして太鼓!オコト!ベース!「ウオオーッ!」乱闘が始まった!
「回転スシが!皿に無い!おれのところに回ってこない!昨日おれは理由を知った!イタマエの近くの奴が!スシを食べ過ぎる!」ユシミは吠える!それはメロディーなどとは無縁の叫び!唸りである。フロアでは、「ウオオーッ!」「執行!」「グワーッ!」「マッポの暴力だ!」「ウオオーッ!」
繰り出される警棒!「グワーッ!」パンクスが殴り倒される。彼らは果敢に押し寄せ、マッポを押し、引き、モッシュの波の中に一人、また一人とさらってゆく。さながらそれは渦潮洗濯機に投げ込まれたジュー・ウェアのごとし!「「マワッテコナイ!スシガコナイ!」「コナイ!コナイ!スシガコナイ!」
「情けねえブタどもだぜ!」起き上がったチーフマッポは破壊された拳銃を捨て、電気ジュッテをフルパワー出力で構えた。ゴウ!ジェット音を発しながらブレイズが間合いを一気に詰める。「イヤーッ!」激しい炎によって加速する右ストレート!「イヤーッ!」チーフマッポはジュッテで応戦!
「「グワーッ!」」ブレイズとチーフマッポは互いに叫び声をあげ、たたらを踏んだ。ブレイズのパンチはチーフマッポを捉えたが、ジュッテ電撃攻撃がカウンターしていた。二者は同時に顔を上げ、狂犬めいて睨み合う!「スシを食べすぎるな!」「スシを食べすぎるな!」「スシを、食べすぎるな!」
「スシを食べすぎるな!」「スシを食べすぎるな!」「スシを、食べすぎるな!」ユシミがフロアを睨み下ろす。そして叫ぶ。「暴力!ダセェ!」「「ウオオーッ!」」パンクスはマッポを前後左右に押し流し、モッシュの波に取り込んでいく。彼らは拳を飛ばさなかった。それは荒々しい踊りじみてもいた。
「ヘヘッ」ブレイズは床に唾を吐いた。「そうとも、ダセェ暴力はアタシらニンジャに任せとけ」彼女は呟き、チーフマッポを睨んだ。「隠してンなよ!この野郎!」「チィーッ」チーフマッポは後ずさった。「戦略的撤退!」そして外めがけ駆け出した。「待ちやがれ!」追うブレイズ!
階段を駆け上がり、裏路地!停車してチョウチンを回転させる無人待機パトカーのボンネットにチーフマッポは飛び乗り、「イヤーッ!」飛び越える。「イヤーッ!」ブレイズは追う!チーフマッポはドタドタと走りながら振り返り、ブレイズめがけスリケンを投擲!「イヤーッ!」
「イヤーッ!」ブレイズは飛来するスリケンを焼き切ると、更に追う!チーフマッポは巨漢に見合わぬニンジャらしい敏捷性を発揮し、ブレイズに追いつく事を許さない。「ブヒィー!」チーフマッポは携帯チョウチンを投げつけた。ブレイズのニンジャ第六感が危険を告げる!それはグレネード!
「な……」ブレイズは地面に転がるチョウチンに突っ込むかたちだ!ウカツ!KABOOM!「グワーッ!」チョウチンが爆発!炎がブレイズを包む!「ヒィーヒィーヒィー」チーフマッポは足を止めて振り返り、肩を揺すって笑った。「ようこそ、ようこそ。お望み通り、おっぱじめようじゃねえか」
バチバチと爆ぜる炎が収束し、赤熱する人型のシルエットに吸い込まれていく。やがてブレイズの姿が現れた。「ハァー。ハァー」彼女は激しく消耗し、肩で息をしている。「ハァー」「ワカル、ワカル。ある種のカトン使いにゃ、火は効かねえッてな、俺は詳しいんだ……だが無傷じゃ済まねえんだな?」
「うるせェー!」ブレイズは火の粉を振り払った。「やってやるぜ!」「アイサツしようや」チーフマッポは笑い、オジギを繰り出した。「ドーモ。キングピンです」「ドーモ。キングピン=サン」ブレイズはオジギを返した。「ブレイズです」「イヤーッ!」オジギ終了と同時に警棒攻撃!「グワーッ!」
ブレイズは汚い地面に叩きつけられ、呻いた。「消耗してやがる……消耗してやがる。避けられもしねェ」キングピンは笑い、先ほど殴られて曲がった己の鼻を掴んだ。ゴキゴキと左右に動かし、元に戻した。「クソライブハウス!まさかニンジャ・バウンサーを雇ってやがるとはなァー。ビビッちまうな」
「イヤーッ!」ブレイズは反撃に出た。地を蹴り、炎で勢いをつけた回し蹴りを放つ!「イヤーッ!」キングピンはこれをブリッジ回避!下から蹴り上げる!「イヤーッ!」「グワーッ!」吹き飛ぶブレイズ!「お前、セクトのニンジャじゃねェな。衛星組織の連中にもテメェのような奴は聞いた事がねェ」
キングピンは警棒を弄びながら言った。「俺はよ、大嫌いなジョギングまでして、ワザワザおまえをこんな場所まで連れてきたんだ。お友達の居るところによ……俺は万全を期するタイプでよ……一対一だと、ヘマこいちまう可能性があるからな。ワカル?」彼は周囲を見渡す。
二人はライブハウスの裏路地よりも更に奥まった場所に来ていた。右手には、金網で仕切られた資材置き場。左手には薄汚い廃ビル。ビルには「サロン営業中」と書かれたノレンがかかっているが、明らかに営業店舗は無い。ブレイズは切れた口を拭い、起き上がってカラテ警戒する。
「そいつがエサか?」廃ビルの屋上で影が蠢いた。「イヤーッ!」影は回転ジャンプで飛び降り、キングピンとブレイズを挟む位置に着地した。ツヤのある紫色のニンジャ装束を着たニンジャはメンポの奥でほくそ笑んだ。「ドーモ。ダチュラです」「ドーモ、ダチュラ=サン」キングピンは笑った。
「マッポのお前に楯突くなんて、ナメたニンジャがいたもんだなァ?」アイロニーじみた言葉が廃ビルの闇の中から聞こえた。そこから現れたのは黄色と黒の警戒色装束のニンジャだ。「ドーモ。ポリスティナエです」「全くだぜ、ポリスティナエ=サン」キングピンは笑った。「困り果てちまった」
「ドーモ。ブレイズです」ブレイズは憎々しげにオジギした。三人はブレイズをトライアングル状に包囲する。「ここはいわば、俺らのオフィスでよォ」キングピンは言った。「表の連中にゃあちと刺激の強い問題を解決する……大事なビジネスの場だ。お前のような手に負えねえ奴を始末する場でもある」
「ニンジャの女とは実際珍しい」ダチュラが言った。装束に巻き付くチューブの中を蛍光色の液体が葉脈めいてめぐり、ポタポタと地面に滴り落ちる。「薬物でしっかりやろう」「だな」ポリスティナエが頷く。その両肘と両膝から危険なニードル状の武器が展開した。キングピンは注意深く間合いを離す。
「最初に攻撃を当てた奴が優先前後だぞ。いいな?」とポリスティナエ。キングピンは頷いた。「好きに……」「イヤーッ!」ドウ!ブレイズの眼前に火の輪が出現した。ブレイズは跳び、その輪をくぐると、一瞬にしてキングピンの真正面に出現していた。拳がキングピンの鼻面を捉えた。「グワーッ!」
不意をつかれ、尻をブレイズに向けてうつ伏せに倒れ伏すキングピン!ダチュラが跳びかかる!「イヤーッ!」毒液したたる両腕がブレイズに伸びる!「イヤーッ!」ブレイズは手の平からジェットじみた炎を放ち、その勢いで強烈な肘打ちを繰り出した。「グワーッ!」そこへポリスティナエが迫る!
「イヤーッ!」ブレイズはポリスティナエに蹴りを繰り出す!「イヤーッ!」ポリスティナエは紙一重でこれを躱すと、ブレイズの脇腹にニードルを突き刺した。「グワーッ!」さらに前蹴り!「イヤーッ!」ブレイズは躱そうとするが、遅い!「グワーッ!」吹き飛ばされ、金網に衝突!
「どんどん回るぞ、毒がな」ポリスティナエは余裕ある口調で言った。「なかなかのカラテをしていやがった」ダチュラは首をボキボキと鳴らしながらブレイズに近づく。「そうだぞ、油断ならねえんだ、そいつ」キングピンは起き上がり、警棒を再び手にした。「油断するんじゃねえぞ。油断はダメだ」
「その物言いは俺の麻痺毒を愚弄することになる」ポリスティナエは肩をすくめた。「見ろ。目もうつろだ。効いている。あとはダチュラの薬物でしっかりやるだけだ」「フン」キングピンは鼻を直しながら、「とにかくちゃんとやれ」と言った。ダチュラがブレイズの首を掴み、金網に押し付けた。
長身のダチュラはブレイズの身体を上へ吊り上げる。両足が宙に浮いた。無力である。朦朧とする意識の中、ブレイズはダチュラの手首を掴み、抵抗しようとした。「無駄だ」とダチュラ。チューブが生き物じみて鎌首を擡げ、先端の針で頸動脈に注射しようとする。ブレイズは呻いた。「ナメるなよ……」
三人のニンジャはゲラゲラと笑った。ブレイズは意識を保とうとつとめた。憤怒を燃やせ。アタシはニンジャだ。諦めるな。侮らせはしない!二度と!彼女のニューロンがスパークし、ニンジャソウルと闘争心が深く繋がった。その瞬間!「グワーッ!?」ダチュラが悲鳴を上げる!
彼女の手はマンリキめいた力を取り戻した。ほんの一瞬のことだった。だが、十分だった。千切れるほどのニンジャ握力で、ダチュラの手首を握りこんだ。怯んだダチュラは高く吊り上げていた彼女を地におろした。彼女は踏み込み、その顔面を思い切り掴んだ。「イヤーッ!」「アバババーッ!?」
痙攣しながらダチュラは頭を抱え、後ずさる。ブレイズは地面に膝をついた。「イヤーッ!」そこへ襲いかかるポリスティナエ!肘のニードルを繰り出す!「イヤーッ!」「何?」キングピンが怪訝そうに片眉を上げた。「グワーッ!」ポリスティナエは横腹を蹴られ、金網に叩きつけられた。ダチュラに!
「てめェ!」キングピンが駆け寄る。「イヤーッ!」ダチュラは振り向きざまにその鼻面へパンチを叩き込む!「グワーッ!」不意をつかれたキングピンはキリモミ回転!尻を向けてうつ伏せに突っ伏した。「何しやがる!?」「何ッてお前……ヘッ」ダチュラは鼻で笑った。「インガオホーだぜ」
「ウヌーッ!」ポリスティナエが金網から身をもぎ離した。目の前には体制復帰したブレイズが立っていた。カッと見開いた両目には憤怒の炎が燃え、その肘先は白熱し、焔を噴き出していた。彼女は口の端を歪めて笑い、拳を握りこんだ。「やるよな?オイ」「貴様……」「イヤーッ!」「グワーッ!」
「イヤーッ!」「グワーッ!」「イヤーッ!」「グワーッ!」ブレイズはジェットじみたパンチを繰り返し叩きこむ!そのたびポリスティナエは金網に叩きつけられ、バウンドして戻り、再びパンチを受ける!「イヤーッ!」「グワーッ!」「イヤーッ!」「グワーッ!」「イヤーッ!」「グワーッ!」
「オイッ!」殴りながらブレイズはダチュラに向かって叫んだ。「どうやって出てきた?イヤーッ!」そしてポリスティナエを殴る。「グワーッ!」「さあな」ダチュラは答えた。「考えるのは後にしようぜ」「そっち、抑えとけよ!」「ああ任せとけ!」ダチュラはカラテを構えた。「調子イイぜ!」
「テメェー」キングピンは警棒で警戒する。「ダチュラ=サンじゃねえな。テメェー」「ああ違うね」ダチュラは……否、そのニンジャは不敵に頷き、あらためてアイサツした。「俺はシルバーキーだ」
5
「シルバー……何?」キングピンは分厚い唇を歪め、不可解そうに顔をしかめた。「ドーモ、キングピンです……ジツ使いか?どこから湧いて出やがった。テメェの名前も、俺の警戒ニンジャリストにはねェな……」「ウープス、ウープス」シルバーキーはダチュラの薬物チューブを引きちぎる。「嫌だねェ」
「イヤーッ!」「グワーッ!」「イヤーッ!」「グワーッ!」その背後では、ブレイズがポリスティナエをフェンスにバウンドさせながら殴り続けていた。キングピンはガムを吐き捨て、彼女めがけおもむろに発砲した。BLAMN!「イヤーッ!」ブレイズはこの驚くべき早撃ちを危うくバック転回避!
「やるな」とシルバーキー。「ハヤイ」「ハヤイじゃねェよ!」ブレイズが叫んだ。「こっちに向けンな!」「寝てンじゃねえぞ、ポリスティナエ=サン!」キングピンもまた仲間を罵った。「何のためにテメェのような連中を遊ばせてやってる」彼のしわがれ声には不気味な迫力があった。
「イ……イヤーッ!」ポリスティナエがフェンスから身を引き剥がし、カラテを構え直す。「なぜ俺の毒が効かんのだ?」「アアッ?」ブレイズの目が怒りに燃えた。身体のあちこちから炎が噴き出し、火の粉が舞う。「毒?そんなもん、焼けちまったンじゃねえの?今アタシ体温何度あるのかな?」
「バカな。焼いただと?血中……」「昔と勝手が違うカトンだけどさ」彼女は拳を握り、開いた。「馴染んで来たよ。改善(インプルーブド)だな。何だっけ?テメェの名前。運が無かったよな。もっともっと殴ってやるからな!」「イヤーッ!」ポリスティナエが飛びかかる!「イヤーッ!」「グワーッ!」
繰り出されるポリスティナエの膝蹴り・肘打ち攻撃コンビネーションに対し、ブレイズの飛び膝蹴りが先んじた。カトン・ジツの運動能力への転用!その速さ!ポリスティナエは顎を上向け、仰け反る。そこへ回し蹴り!「イヤーッ!」「グワーッ!」ポリスティナエは背中からフェンスに衝突!
「イヤーッ!」跳ね返るポリスティナエにブレイズが拳を叩き込む!「グワーッ!」「役立たずめが!」キングピンが再び拳銃を構える!「イヤーッ!」「グワーッ!?」キングピンは手の甲をシルバーキーに打たれ、拳銃を取り落とす!「俺だぜ。お前の相手はな」「てめェー!イヤーッ!」警棒攻撃!
「イヤーッ!」シルバーキーは警棒を片腕で防ぎ、キングピンの顔面を鷲掴みにしようとする!「イヤーッ!」キングピンのニンジャ第六感はシルバーキーのグラップリング攻撃に不穏な気配を察知し、バックフリップで回避!空中で一瞬丸いボールめいた後、砂煙を立てて着地する!
「イヤーッ!」BBBLAM!キングピンはサブウェポンであるハンドガンを腰だめ連射!「イヤーッ!」シルバーキーは両腕をクロスし、盾となる!背後ではブレイズがフェンスから跳ね返ってくるポリスティナエを繰り返し殴り続ける!「イヤーッ!」「グワーッ!」「イヤーッ!」「グワーッ!」
BLAMBLAM!BLAM!「グワーッ!」シルバーキーは呻く。ハンドガンがダチュラのニンジャ装束を撃ち抜き、ダメージを与える!キングピンはシルバーキーを睨んだ。「この野郎……」「ああそうさ」シルバーキーは言った。「俺は痛くも痒くもねえ。こんなクソ野郎の身体がどうなろうとな」
その言葉は果たして本当だろうか。目から出血しながら、彼は叫んだ。「やれ!ケリをつけちまえ!」「イイイヤアーッ!」ブレイズのパンチが加速!ポリスティナエからフェンスに熱が伝わり、赤熱して変形!ブレイズは拳を開き、握り、また握り込んだ。そしてカイシャクの一撃!「イヤーッ!」
「……サヨナラ!」熱で焼き切られたフェンスごと、ポリスティナエの身体が後ろに倒れ込んだ。そして爆発四散した。「ブヒッ……」キングピンは引き金をカチカチと引きながら後ずさる。アウトオブアモー。「オイオイ……何で俺様が劣勢なんだ……仕方のねえ奴らだぜ!」身を翻す!
「おう!また俺たちの前にナメた真似しに来やがったらな!覚えてやがれよ!」シルバーキーはキングピンの背中を指差し叫んだ。「"俺たち"は他にもまだまだいるぜ!もっとヤバイ奴がな!」「黙れ!」キングピンは走りながら振り返り、罵った。「今日のところは勘弁してやる!オタッシャデー!」
ザンシンを終えたブレイズはシルバーキーに駆け寄った。「オイ!何で逃がしたんだ。バカな事しねぇように、痛めつけるか脅しのネタを取らなきゃだろ!」「そうしたいのは山々だったが……」ブレイズは振り返ったシルバーキーの肩をドンと衝く。シルバーキーは仰向けに倒れた。「限界みたいだ」
ブレイズは狼狽し、倒れたシルバーキーを揺さぶった。「オイ!」「ダイジョブだ、ダイジョブ」シルバーキーは呻いた。「死にやしないさ。コイツの身体、カラテで鍛えられてるし、頑丈だ」「オイ!」「だからさ……」シルバーキーの震える手が差し上げられた。「手を」ブレイズはその手を掴んだ。
「すまねえな……やっぱり謝らずにはいられねえ」シルバーキーは呟いた。ダチュラの身体は糸が切れたように力を失い、だらりと倒れた。「オイ!」ブレイズはダチュラの身体を揺さぶる。動かない。「オイッ!」動かない。……やがて彼女は立ち上がった。
「……」彼女の赤い髪に、波紋めいて、黒い色が走り、また赤くなった。ブレイズの表情から次第に狼狽と悲哀が去り、しかめ面に変わった。彼女は近くのゴミバケツを蹴り飛ばした。「紛らわしいんだよ!カス!」彼女の髪に再び黒い色の波紋が走った。彼女は弁明めいて言う。「いや、本当すまねえ!」
一人芝居じみて、彼女は己と会話した。その髪には黒い波紋が繰り返し走り続ける。「今のはギリギリだったかもしれねえ。実際死にかけてた。ああまでなっちまうと、直接触れないと。回収してくれてよかったよ」「そうかよ。それじゃ、お前を捨てていけば、アタシは自由になれたって事か?」
「いや、そこがわからねえんだ。君だけで生命維持ができるのか、何ていうかさ、説明が難しい……心苦しいが……」「出てけよ!方法を調べるんだろ?そしたら出てけよ!」「勿論だ!」彼女はうけあった。そして水溜りに己を映し、穏やかに言った。「な。どうにか頑張ろうな」……髪の黒色が消えた。
◆◆◆
ブレイズはバーカウンターを背にして床に座り、モップがけをするダブルモヒカン青年の動きを目で追っていた。割れた瓶や脱ぎ捨てられた衣類、気絶して起きないパンクス、瓦礫の類は脇に寄せられ、DJは客を追い出すレコードを既に流し終え、退出していた。
「ま、色々あったが」オーナーは満足げに言った。「悪くねえオシマイだったんじゃねえか?」「そうね」ブレイズは頭をボリボリと掻いた。オーナーは頷いた。「俺は隠居だ。お前らはお前らで、まあ、よしなにやっていけや」「勿論ですよ」ダブルモヒカン青年がモップ速度を上げる。「絶対ですよ!」
ダブルモヒカン青年は言った。「ユース・パワーですよ!俺ら……ハコが壊されたって、俺ら、死なねえですよ。俺らが死んでも言葉は残りますよ。俺、貯金していますから。堅実なパンクスだから。絶対、ヨタモノ、俺らがまた始めますし」「ああ、それがいいよ」オーナーは頷いた。「まあ頑張れ」
「ブレイズ=サン、連絡先教えてよ」ダブルモヒカン青年が言った。「ア?」「トレジャー・エヴリー・ミーティング。これも何かのアレだよ。ヨタモノ復活したら、セキュリティしてよ」ブレイズはアクビをした。「考えとく」「ユシミにはアイサツしたか」とオーナー。「感銘受けてたじゃねえか」
「いや、いいよ」ブレイズは答えた。「暴力ダセエから……」「気にしてンだ!」ダブルモヒカン青年が笑顔を向けた。ブレイズはコースターを投げつけた。「なあ。本当にやれよ。やってみろ。な」オーナーが彼らに向かって言った。「そうすりゃ、俺もこのハコも、居た甲斐があるって事なんだぜ」
「フス……」オーナーの隣で車椅子の男が同意めいて呻いた。ブレイズはそちらを見た。今までそこにその男が居た事に気づかなかったのだ。外で戦っている間に入場していたのか。オーナーの友人じみたその男は目を動かしてブレイズとダブルモヒカン青年を見、そして笑った。彼の手には中指しかない。
「マジかよ」ブレイズは呟いた。「絶対やりますよ!任してくださいよ」ダブルモヒカン青年はモップ速度を更に上げながら、興奮して繰り返した。階段の上、店の外でけたたましくクラクションが鳴った。「お迎え、来たぜ」オーナーは男に言い、車椅子を押した。
ブレイズの前を通り過ぎる際、車椅子の男はブレイズに中指を立てて見せた。男は笑っていた。ブレイズの胸中に様々な感情が去来した。彼女は歯を剥き出して笑い返し、キツネサインを返した。
【ワン・ガール、ワン・ボーイ】終
N-FILES(設定資料、原作者コメンタリー)
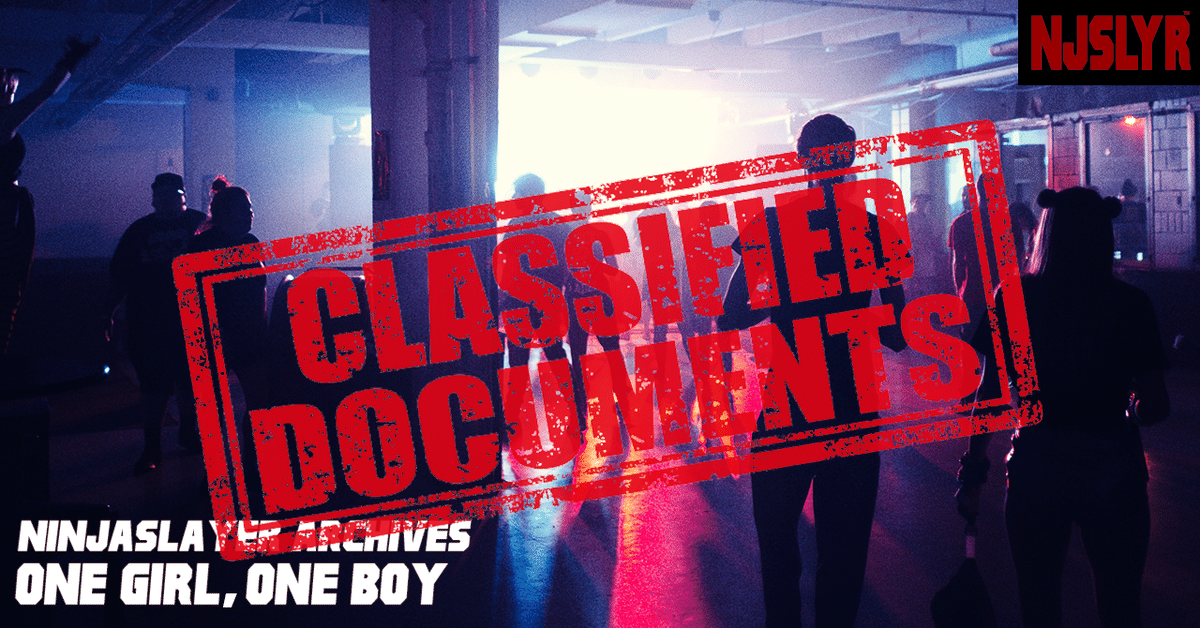
ここから先は
この記事が気に入ったらチップで応援してみませんか?

