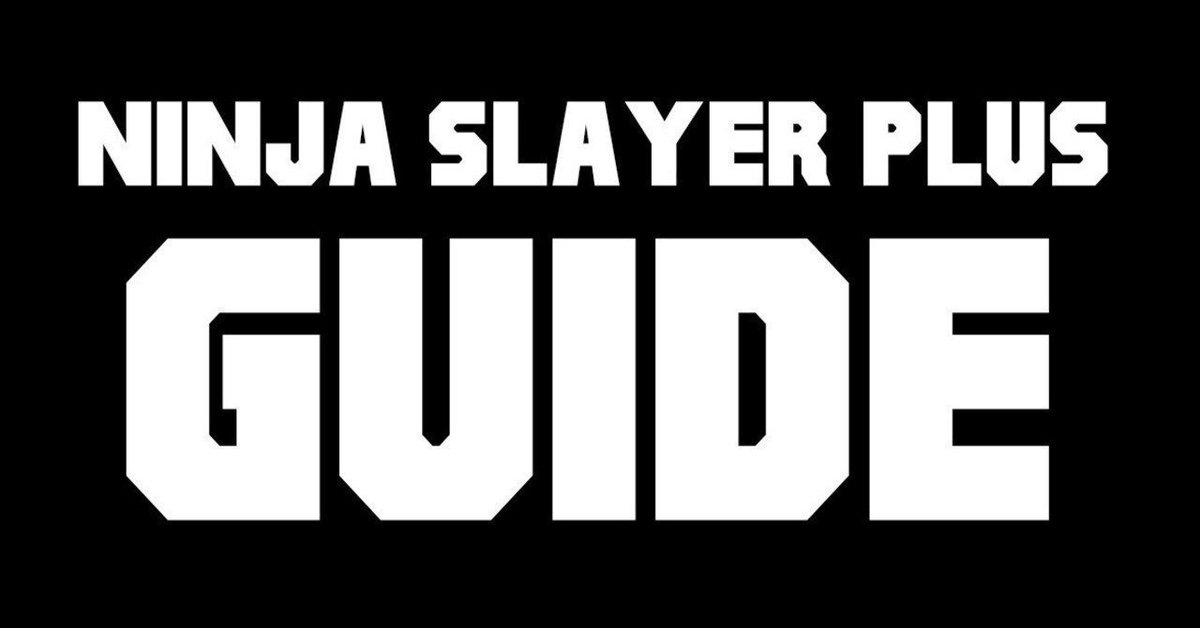チャブドメイン・カーネイジ
この小説はTwitter連載時のログをそのままアーカイブしたものであり、誤字脱字などの修正は基本的に行っていません。このエピソードの加筆修正版は、上記リンクから購入できる物理書籍/電子書籍「ニンジャスレイヤー ネオサイタマ炎上2」で読むことができます。
ニンジャスレイヤー第1部「ネオサイタマ炎上」より
【チャブドメイン・カーネイジ】
インターラプターとの死闘に辛くも勝利したニンジャスレイヤー。死に際にインターラプターが残した「ユカノの行方を知りたくば、相撲バー『チャブ』のマイニチ=サンに会え」という言葉を、彼は聞き逃しはしなかった。
ダークニンジャの襲撃により行方知れずとなったユカノの無事を確かめねば、ニンジャスレイヤーはあの世のドラゴン=センセイに顔向け出来ない。ニンジャスレイヤーは傷の癒えない身体をおして、相撲バー『チャブ』へ向かう。
リョウゴク・ストリート、PM8。
ネオサイタマにおけるスモトリ興業を一手に引き受けるコロシアム・シティ、それがリョウゴク・ストリートである。
チャンコ072を長期に渡りドープすることで異常巨体を手にし、コロシアムで血みどろの殺し合いを繰り広げることを運命づけられた者たち。それがスモトリである。
チャンコ072は遺伝子異常を誘発する深刻なリスクがある。しかし残念ながらこの企業支配社会において、効率という概念は人権よりも重んじられる。ネオサイタマ郊外のジャングルには遺伝子異常の果てに知性を失い、廃棄されて野生化したスモトリ達が獣のように暮らしている。
リョウゴクのコロシアムでしのぎを削るスモトリ達はその手のルーザーとは一線を画する存在だ。力は権力を、金を、セックスを、ほしいままにする。中央リーグ「リキシ」のドヒョウに上がれるのはわずか64人。勝ち続ける事でその地位を手にしたリキシ・スモトリ達は、貴族同然の暮らしを送っている。
リョウゴク・ストリートに軒を連ねる相撲バーは、興業中は連日連夜、血に飢えた観戦者達でごったがえす。バッファロー肉とスモトリ・チョコに舌鼓を打ちながら、巨大なスクリーンで中継される相撲ファイトに歓声をあげるのだ。
相撲バー「チャブ」はリョウゴク・ストリートでも一番の老舗を標榜している。改築を繰り返した巨大な店構えは、誇り高く木彫りされた「お相撲」の看板に恥じない。複数のカウンターを擁した一階のホール、高級コタツが配置された二階のバルコニー席。
酔漢でごった返す一階ホールへ、今、入り口の両開きのドアを開けて入ってきたものがいる。目深にかぶったハンチング帽、草色のトレンチコート。むろん、その姿へ関心を向けるものなどいない。
トレンチコートの男は巨大スクリーンの脇を通り、第二カウンターへ歩いて行った。立ち飲みの客達でごった返すホールであったが、男は避けるそぶりすら見せず、なおかつ、誰ともぶつかることなく、スムーズに前進する。
男はカウンターでバリキ・カクテルをシェイクするバーテンに声をかけた。「マイニチ=サンは?」初老のバーテンは無関心な目をトレンチコートの男に向ける。「今、裏でタバコ吸っとるよ。もうすぐ休憩の交代だから、ここで待ってな。ご注文は」「トックリを」「トックリね」
バーテンはトックリ・サケをカウンターに置いた。トックリの口にはカボスが挿してある。男はトークンをバーテンに手渡した。
そのとき、店内の照明が落ち、巨大スクリーンがネオンサインとともに点灯した。ネオンサインは「お相撲」「リキシ」「闘争心」といった言葉である。「本日のセンシュラクです」マイコ合成音声が告げると、ホールが歓声で沸き立った。
スクリーンに大写しになった巨人はナンバー4ランカーのリキシ・スモトリ、ダイポンギである。その身長は10フィートはあろうか?筋肉と脂肪で膨れ上がった巨大な身体、そして鉄仮面が写ると、人々が狂ったように叫び出した。「ダイポンギ!」「今日こそヤッチマエー!」
黒光りする肉体は、鉄仮面とマワシを除けば一糸まとわぬ裸体である。胸板の「スゴイ」というタトゥーが禍々しい。これほどの巨体を作り上げるために、どれほどのチャンコ072をドープしてきたのであろうか?鉄仮面の呼吸孔から真っ白い蒸気が噴き出す。ダイポンギが睨みつける花道にライトが点る。
「チャブ」の店内が水を打ったように静まり返った。花道をドヒョウ・リングへ向かってゆっくりと歩いてくる人影。その背格好は常人の身長の範囲だ。6フィートといったところである。しかし、マワシひとつの肉体から滲み出す燃え上がる鋼のような質量感はスクリーン越しにも伝わってくる。
「畜生、あんなカラダで勝ちまくりやがって」誰かが憎々しげに毒づいた。そう、このスモトリらしからぬ男こそがナンバー1ランカー、すなわちヨコヅナ。目下102連勝中のおそるべき男「ゴッドハンド」であった。
ドヒョウ・リングの真上へ、鎖で吊られた鉄の棍棒が降りてくる。今回の試合のアチーブメント・ウェポンだ。試合中にあの武器を手にすれば、大きく有利を得ることができる。「両者、準備して!」ジャッジの音声が会場に響き渡る。
ダイポンギは前傾姿勢をとった。試合開始と同時に、その巨体によるタックルをぶつけるつもりなのだ。呼吸孔から蒸気が吹き上がり、肩の筋肉がわなないた。そのさまはまさに鋼鉄の機関車である。
「ハジメテ!」ジャッジが叫んだ。ダイポンギがゴッドハンドにタックルをしかけた。並の人間が受ければ全身が粉砕骨折して即死に至ることは明白な攻撃だ。しかし、おお、なんということか。ゴッドハンドは前に突き出した両手で、ダイポンギの巨体を真っ向から受け止めて見せた。
「ああっ……」スクリーンを見守る観衆からため息が漏れる。スモトリ最大巨体を持つダイポンギの突進ですら動かせないゴッドハンドは、まさに規格外の存在であった。ゴッドハンドの背中の筋肉が盛り上がり、少しずつダイポンギの圧迫を押し戻し始めた。
決着がついたのは、ゴッドハンドが押し戻したと見えた、そのわずか一秒後であった。ダイポンギの体が空中でキリモミ回転をしながら真上に吹き飛んだ。そして空中のアチーブメント・ウェポンを支える鎖とケージに叩きつけられ、ずたずたに裂けた巨体は無残な肉塊となりはてた。
「キマリテ、上手投げ。勝者ゴッドハンド」ジャッジの声が、静まり返った会場、そしてスクリーンを見守る「チャブ」の人々の間に響き渡った。
スクリーンが中継からコマーシャルに切り替わった。「かっこいい服は今にもまとまりやすい!」バイオ洗剤の寸劇コマーシャルの明るい音楽が流れるが、人々はオツヤ・リチュアルのように静まり返っていた。103連勝、ゴッドハンド。相撲の破壊者。誰も彼に勝てはしない。棄権せねば、死あるのみ……。
「あれじゃ、誰も相撲を見なくなっちまう。そう思わないか?お客さん」いつのまにか奥から出て来ていたスキンヘッドのバーテンダーが、トレンチコートの男に声をかけた。「あいつは強すぎるよ。まるで……」カウンターから身を乗り出す。声をひそめる。「まるでニンジャだ」
トレンチコートの男が身を固くした。スキンヘッドのバーテンダーは芝居がかった仕草でオジギした。クローム製のオジゾウ・ネックレスがチャリチャリと音を立てた。「ドーモ、ハジメマシテ、ニンジャスレイヤー=サン。ヒロ・マイニチです」
「な……」トレンチコートの男は、アイサツ返しすら忘れる程の衝撃を受けたようだった。さもありなんである。「なんだと?」「気にすることはない。あんたの偽名はなんだったかね?忘れちまったもんで」マイニチ=サンはにやりと笑った。
「驚くことはない。種明かしをすると、インターラプター=サンから伝書鳩を受け取ったのだ。彼があんたを襲う一時間前にな。あんたに情報をくれてやれと書かれていた。インターラプター=サンは死を覚悟していたのかもしれん」
トレンチコートの男……ニンジャスレイヤーは、油断ならぬ視線をマイニチ=サンに向けた。「では、おれの目的もわかっているな」「勿論。安心するがいい、情報代はツケにしておいてやるさ、あんたの噂はおれのネットワークを通じてしばしば耳に入ってるからね、凄腕だってね……」
「では、おれが今までどんな殺し方をしてきたか、知っているな。もったいつけるな。マイニチ=サン」「ぶ、物騒だぜ、お友だち……」マイニチ=サンはぶるぶると震えて見せた。それもまた芝居がかっている。
マイニチ=サンはベストの内ポケットから、フィルム状の記憶素子を取り出した。「さほど困難なビズ(仕事)じゃなかったぜ。お友達……。ここにユカノ=サンの情報がある」そして、意味ありげに付け加えた。「あんたの望むものは、そこにあるかね……」
ニンジャスレイヤーはマイニチ=サンの手から素子をひったくった。「どちらにせよ、真偽はすぐに確かめる。偽りならば……」「そこは信頼してくれていいぜ。俺はプロさ、 時間さえあれば、あんたと犬猿の仲のあのソウ…ソウ…ウ…ウ…」
マイニチ=サンがブルブルと震え出した。「ウウバァーゴボボボ!」泡状のヨダレをゴボゴボと吹き出しながら、マイニチ=サンがいきなり拳銃を取り出しニンジャスレイヤーに向けた。「イヤーッ!」反射的にカウンターの上へジャンプしたニンジャスレイヤーが、マイニチ=サンの側頭部へ回し蹴りを放つ。
「アバーッ!」マイニチ=サンのスキンヘッドの頭部が横なぎに吹き飛び、くるくると回転しながら宙を飛んだ。丸い頭はホールの片隅にある相撲スロット・マシンのレバーにぶつかり、極太ミンチョ体フォントが図柄となったドラムを回転させた。「お」「相」「撲」。
「ひゃあ!やったあ!今日は朝からこの席をキープしてたんだぜ!」そのスロットマシンの席に陣取っていた中年男が楽観的な歓声をあげた。スロットマシンからは相撲コインが際限なく溢れ出してくる。「まったく生首サマサマだよ!これで三日分の負けがチャラ……ララー!」おお、見よ!
その中年男もまた、マイニチ=サンのようにアブクを吹きながら、バネじかけのように席から立ち上がると、ぎこちない手つきで腰のピストルを抜き、ニンジャスレイヤーへ向けた。「イヤーッ!」「アバーッ!」脳天に、ニンジャスレイヤーの投げたスリケンが突き刺さった!
今度はその相撲スロットの近くのテーブル席に座っていた三人のノミカイ・サラリマンである。それぞれの額にネクタイをしめたほろ酔いのサラリマンが、一斉にその手の吹き矢を構えた。「イヤーッ!」「アバーッ!」「アバーッ!」「アバーッ!」スリケンが、サラリマンの脳天に突き刺さった!
「非常事態だ!」黒服が胸のIRCトランスミッターへ手を伸ばそうとするが、その手は急に震え出し、かわりに取ったのは拳銃だった。「連絡、くくく、く」「イヤーッ!」「アバーッ!」スリケンが、黒服の脳天に突き刺さった!
今やホールの客と従業員すべてが、思い思いの武器を手にニンジャスレイヤーに狙いを定めていた。いや、ホールだけではない。上階のバルコニーで悠々とポン酒を飲んでいたカネモチ達も同様であった。機関銃を構えた老婆すらいる!
集中砲火が始まった。スモトリをかたどった相撲ブランデーのボトルが、グラスが、相撲チョコの壺が、ガシャガシャと音を立て弾け飛ぶ。ニンジャスレイヤーは火線を避け、カウンターの反対側へ身を踊らせた。多勢に無勢!
「フーム、フム、フム、フーン、フム」ニンジャスレイヤーを包囲する群衆の後方、ふんぞり返ってその地獄図を見守る者があった。薄紫の装束。ニンジャである。「噂通り、一筋縄ではいかぬか、ニンジャスレイヤー=サン。ロートルとはいえ、あのインターラプターを殺っただけのことはあるか」
その背後に、ステルス装束の別のニンジャのシルエットが滲み出す。「初手はよし、だな。インフェクション=サン」「フム」「入念な準備もダイダロス=サンのハッキング技術あればこそ。奴にフーレイしておくか」「そうよのう、ヴィトリオール=サン。だがおぬしにも存分に働いてもらうぞ」「勿論だ」
ステルス装束のニンジャ「ヴィトリオール」は静かに頷くと、再び闇の中へ戻って行った。「フーンフム、ホーム。次の一手と行こうか」インフェクションは一人呟いた。作戦名「チャブドメイン・ギャンビット」。
作戦の取りかかりは情報屋ヒロ=マイニチ。彼の日頃の情報収集は、ソウカイ・シンジケートにツツヌケであった。彼は踏み込み過ぎた。そして虎の尾を踏んだのだ。ソウカイヤの情報ドメインを……もっと言うならば、電脳ニンジャ、ダイダロスが電子情報の海に撒き散らした電脳ブービートラップを。
ユカノという女の居場所を探るマイニチ=サンの動きは、初めは見過ごされるべき小さな波紋に過ぎなかった。だが、インターラプターの死を手がかりに、やがてその動きはニンジャスレイヤーの存在と結びつけられる事となった。
事が起こる6時間前に、既にダイダロスはニンジャスレイヤーが相撲バー「チャブ」へ訪れるであろう確定的な情報をつかんでいた。入念なニンジャブリーフィングを経て、この二人のニンジャ、インフェクションとヴィトリオールがチャブに派遣され、手ぐすね引いて待ち受けていたのである。
インフェクションは左手のひらを上に向けた。おお、なんたる不気味!ニンジャ小手の隙間からインフェクションの手のひらに這い出てきた白い多足虫は、なんであるか!?これこそは彼が体内に飼う「コントロール・パラサイト・ムシ」である!
賢明なる一部の読者の皆さんは、その多足虫の謎めいた名称から答えを導き出していた事だろう。そう、現在このチャブの客と従業員すべてを支配下におき、操り人形がごとく自由自在に動かしているのは、一人一人の脊髄に潜り込んだこの悪魔的な虫型バイオ神経強制操作システムの働きによるのだった。
インフェクション自身は非力なニンジャであるが、最大1008匹のパラサイト・ムシを同時に操作する事ができる。これは彼に憑依したニンジャソウルの適性と、リー先生が行った前頭葉バイオ手術の相乗効果だ。コントロールされた生物は精密な動きはできぬが、銃の引き金を引くくらいはやってのける。
さしものニンジャスレイヤーといえど、この建物にごったがえす全ての群衆が相手となれば思うように反撃も行えまい。インフェクションは注意深くカウンターの陰を注視しながら、次の一手へ向けて脳波コントロールの意識を尖らせた。少しでもその姿を露わにすれば、たちまち蜂の巣にしてやろう。そして……。
「ハッキョホー!」「ハッキョーホー!」野太い声が店内に轟いた。なんたることか!地響きと共にインフェクションのもとへ駆け寄ってきた二人の巨漢は、オシノビでチャブにやってきていた休場中のリキシ・スモトリ、モンタロとコタロではないか!彼らもまたパラサイト・ムシの支配下であった。
ドヒョウ・リングにない彼らはマワシを締めておらず、かわりに黒いレザーのハーフパンツをはき、上半身は全裸である。頭部にはいかつい鉄仮面を装着しているが、口のあたりの空気孔からだらしないヨダレが滴り落ちている。
「フーン、フム、ホーム。こやつらを使って隠れ場所を取り上げてやるとしよう、ニンジャスレイヤー=サン。モンタロ=サン!コタロ=サン!さあ、やれ!」インフェクションがこめかみに指を当て、念じると、二体の凶暴なスモトリは獣じみた呻き声で応えた。「突っ込め!」「ノコター!」「ノコータ!」
二体のスモトリはニンジャスレイヤーが身をひそめるカウンターめがけて同時に突進を開始した。まさにそれはブレーキの壊れた暴走機関車である!動線上にいた数人の客が跳ね飛ばされ、あるいは踏み潰される。しかし悲鳴を上げるものはいない!
モンタロとコタロがカウンターに殺到する。滅茶苦茶な破壊音と震動、土煙。頑丈なオーク材がひしゃげ、飛び散り、相撲チョコと共に四散する。土煙の中、ニンジャスレイヤーは果たしてどうなったのか……!?
「フーン、ホム、残念、残念」インフェクションは腕組みして、晴れつつある土煙の中を見守り、嘆息した。「ま、これで終わるようなら、そもそもこれまでかように我々を出し抜くような真似などできんからな。想定しておるわ」
彼がカウンターと相撲チョコの四散する残骸上に認めたもの、それは、右手でモンタロの頭部を、左手でコタロの頭部をがっちりと掴み、頭突きの突進を押しとどめるニンジャスレイヤーの姿であった!
「忍」「殺」と彫られたメンポ、赤黒いニンジャ装束。ニンジャスレイヤーの背中が筋力の緊張で膨れ上がる。「フンー!」「ノコッタフンムー!」モンタロ、コタロはバッファローのごとき唸りをあげ、ズシリズシリとさらなる前進と圧迫を試みる。しかしニンジャスレイヤーは動かない!
インフェクションはこめかみに指を当て、命じた。「殺れ!スモトリもろとも、蜂の巣だ」途端に、激烈な銃撃の嵐が再開された。しかし、おお、なんたる事か!
「イヤーッ!」ニンジャスレイヤーはモンタロとコタロの仮面を鷲掴みにし、その巨体を同時に吊り上げた。そしてその巨体を肉の盾として、四方八方からの銃撃を遮った。
「グワーッ!」「グワーッ!」「グワーッ!」「グワーッ!」「グワーッ!」「グワーッ!」「グワーッ!」「グワーッ!」「グワーッ!」「グワーッ!」「グワーッ!」「グワーッ!」「グワーッ!」「グワーッ!」「グワーッ!」「グワーッ!」「グワーッ!」「グワーッ!」
銃撃の雨あられを受け、血みどろのモンタロとコタロは水揚げされたハマチよろしく、じたばたと苦しんだ。しかしカウンターの残骸の上に立ってスモトリを吊り上げるニンジャスレイヤーのニンジャ握力はびくともしない。
二人のスモトリが絶命し、もがくのをやめても銃撃は続いた。やがてこのミート・シールドも役に立たなくなるであろうと思われたその時であった。
「イヤーッ!」ニンジャスレイヤーは、モンタロの巨体を放り投げた。狙いは二階バルコニーの支柱である。巨大な肉塊が叩きつけられると、歴史ある木製の支柱にひび割れが走った。
「イヤーッ!」ニンジャスレイヤーは、コタロの巨体を放り投げた。狙いは二階バルコニーのもう一方の支柱である。巨大な肉塊が叩きつけられると、歴史ある木製の支柱にひび割れが走った。
「イヤーッ!」ニンジャスレイヤーは垂直にジャンプした。銃撃がそれを追うが、ニンジャスレイヤーには届かない。彼は背後の壁を蹴って斜めに跳んだ。モンタロが刻みつけたバルコニーの支柱に、飛び蹴りが突き刺さった。
「イヤーッ!」ニンジャスレイヤーは支柱を蹴り、その勢いで、コタロがダメージを加えた反対側の支柱に弾丸の如き飛び蹴りを加えた。
ニンジャスレイヤーは六連続でバック転し、銃撃を躱しながら相撲スクリーンの真下まで後退した。バルコニーの支柱が嫌な軋み音とともに、ひび割れを広げながらかしぎ始める。「なに!?これは…」インフェクションが慌てて頭上を見上げた。天井が…バルコニーが、落ちてくる!
重みに耐えきれなくなった支柱がついに粉砕した。続けて、バルコニーの床がめちゃくちゃに崩れ、銃器を構えた二階のカネモチ客、コタツや相撲チョコもろともに、瓦礫となって一階のホールに降り注いだ。
「グワーッ!」あえなく崩壊に巻き込まれたインフェクションのか細い悲鳴を、ニンジャスレイヤーのニンジャ聴覚は轟音の中で聞き取っていた。バルコニーが完全に崩落し、彼の眼前には瓦礫と死体が残るばかりだった。かろうじて崩落に巻き込まれなかった人々が我に返り、口々に悲鳴をあげた。
虫の息のインフェクションは、瓦礫から這い出ようともがいた。彼のニンジャ能力はパラサイト・ムシのコントロールに特化されている。バルコニーを崩された時点で、彼のチェック・メイトだった。震える手が突き出し、周囲の木屑と相撲チョコを押しのけようとする。その手は無慈悲に踏みつけられた。
「グワーッ!」「ストラテジー・ゲームはおしまいだ、ソウカイヤ」ニンジャスレイヤーはインフェクションの手の甲を踏みにじった。「グワーッ!」「せいぜい這い出すがいい。その後カイシャクしてやる」「グワーッ!」
インフェクションは祈った。ヴィトリオール=サン、今だ、この時を逃すな。奴がワシをいたぶる今この時だ。お前のリキッド・ソードの出番だ……
「イヤーッ!」「イヤーッ!」叫び声と叫び声が重なった。ヴィトリオール=サンがおそらくニンジャスレイヤーの背中にアンブッシュを仕掛けたのだ。任せたぞ、ヴィトリオール=サン。インフェクションはその結末を待つ事なく、死の闇に落ちた。
「グワーッ!」ニンジャスレイヤーの振り向きざまの回し蹴りを受け、ヴィトリオールは真横に吹き飛んだ。ステルス装束のカモフラージュ機構が衝撃を受けてバチバチと明滅する。アンブッシュに失敗した新手ニンジャは空中でくるくると回転し、着地した。
「グワーッ!」ニンジャスレイヤーは両腕から煙を吹き上げ、苦しんだ。ヴィトリオールのカタナ攻撃を躱しつつの回し蹴りを淀みなく行ったニンジャスレイヤーであった。何が起きたのか!?飛沫である。飛沫がニンジャスレイヤーに降りかかったのだ。
「ドーモ、ニンジャスレイヤー=サン、ヴィトリオールです」明滅するステルス装束のニンジャの、頑丈な小手を嵌めた右手から無色の液体が溢れ出す。そしてそれが、おお、見よ!それが空中で固体化し、刃を形作ったではないか。
「ドーモ、ハジメマシテ、ヴィトリオール=サン。ニンジャスレイヤーです」ニンジャスレイヤーはアイサツを返した。腕の火傷傷を意に介さず、ヴィトリオールのもとへ歩を進める。「イヤーッ!」ヴィトリオールが仕掛けた。右手の刃でニンジャスレイヤーの肩口に切りつける。
ヴィトリオールのリキッド・ソードは回避不能の必殺武器である。彼のニンジャ能力は硫酸の固形化だ。たとえ彼の斬撃を防いだとしても、砕けて飛沫となった硫酸は敵の装甲を融かし、皮膚を焼く。ニンジャスレイヤーはしかし、右腕で刃を弾き返した。なんという事を!
途端にリキッド・ソードは砕け、液状化した。飛沫が彼のニンジャ装束を焼き焦がす!「バカめ!初撃で学ばぬはニンジャの恥!おしまいだニンジャスレイヤー!」勝ち誇ったヴィトリオールが、新たに生成したリキッド・ソードで赤黒のニンジャ装束を突き刺す!
「ヤッツケター!……グ、グワーッ!?」ヴィトリオールは、信じられぬ、という目で、己の胸から突き出した血濡れの手を見下ろしていた。ニンジャスレイヤーの手だ。背中だ、背中から貫通したのだ。では彼が突き刺した重みは。リキッド・ソードが捉えた赤黒のニンジャ装束は……
彼の刃に刺さっているのは、もぬけの殻のニンジャ装束だった。「バ……」「ニンジャ殺すべし」背後に立ち、ヴィトリオールの心臓をえぐり抜いたニンジャスレイヤーが言い放った。上半身は裸であった。タツジン!彼は己のニンジャ器用さを発揮し、一瞬にして装束を脱ぎ捨てていたのだ!「バカナー!」
ニンジャスレイヤーはヴィトリオールの背中から血濡れの腕を引き抜き、くるりと踵を返した。立ち去る彼の裸の上半身から汗のように赤黒い血液が染み出し、ひとりでに織り上がって、赤黒のニンジャ装束となった。「サヨナラ!」ヴィトリオールは断末魔の悲鳴をあげ、爆発四散した。
瓦礫の中、ニンジャスレイヤーはゆっくりと歩を進めた。我に返った数えるほどの生き残り客が震えながら見守る中、絶命したインフェクションの頭部を踏み潰すと、そのまま彼は店外へ出て行った。濁った夜の闇の中へと。
【チャブドメイン・カーネイジ】終
「ニンジャスレイヤーPLUS」でヘヴィニンジャコンテンツを体験しよう!
![]()